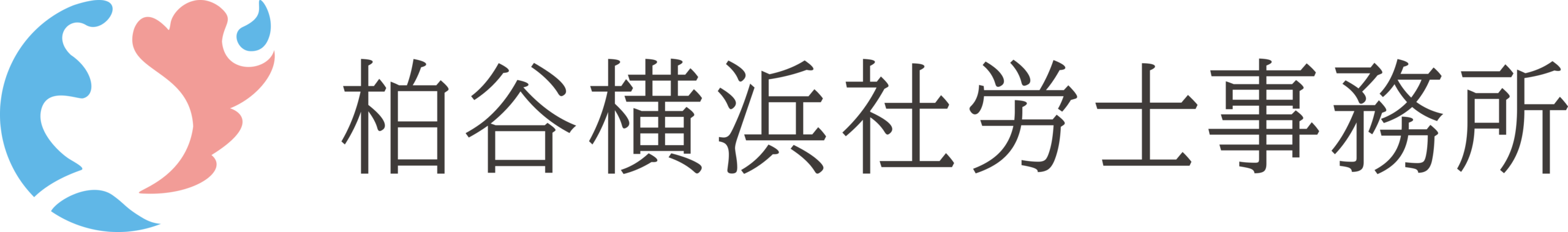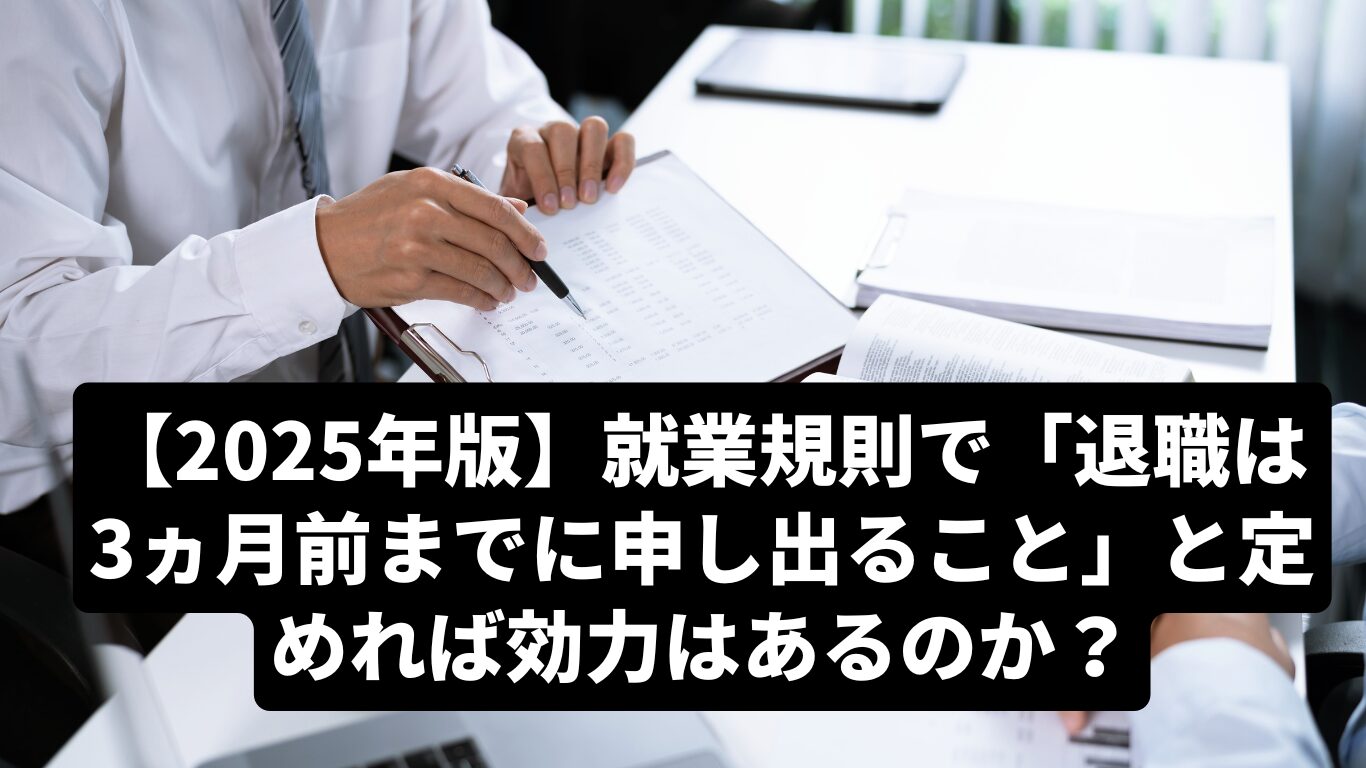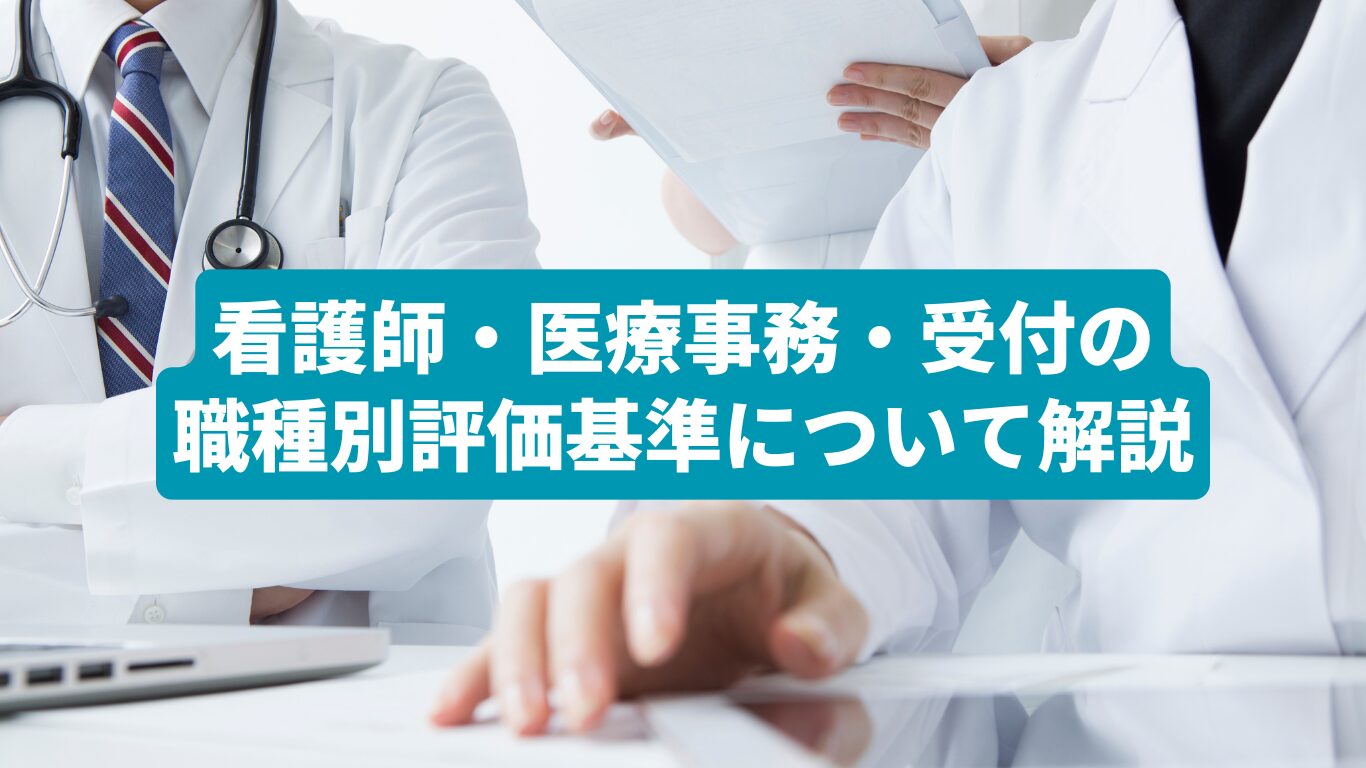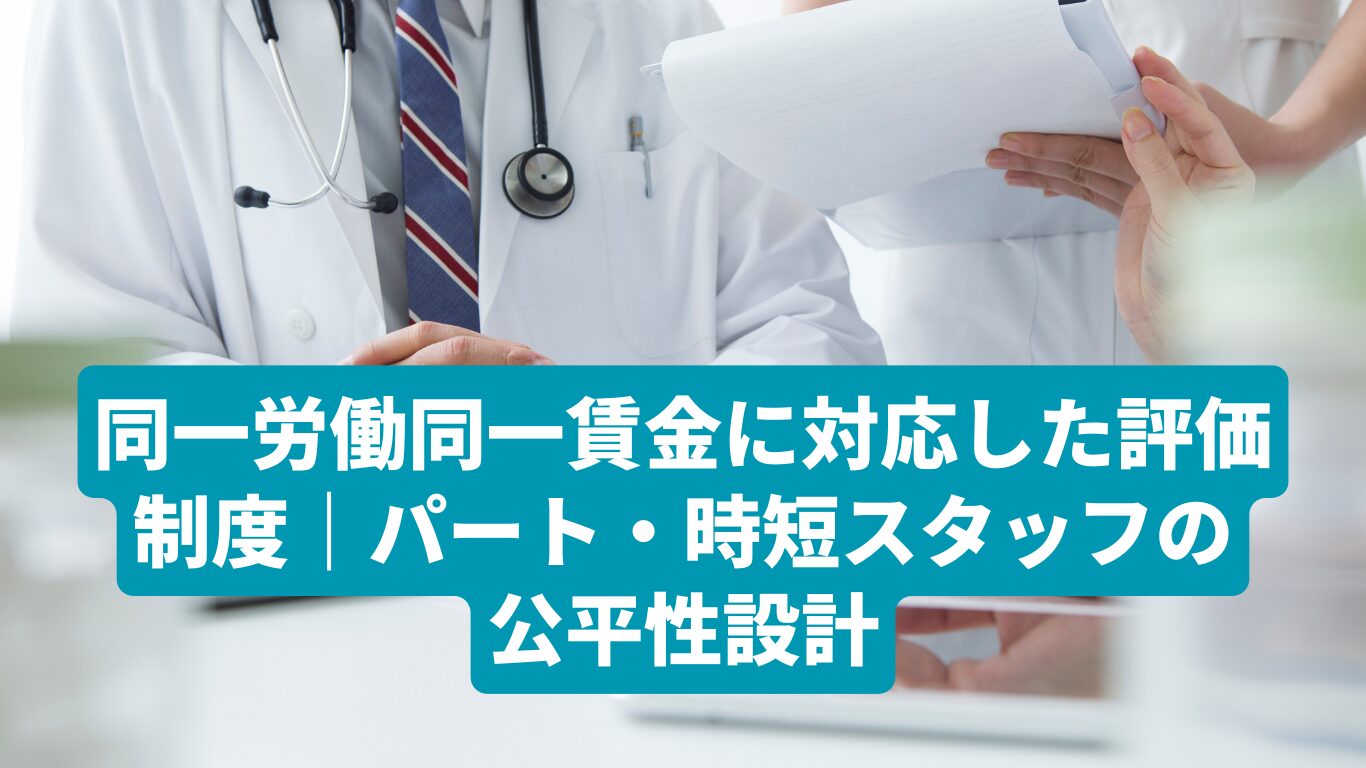「退職は3ヵ月前までに申し出ること」
中小企業の就業規則でよく見られる一文です。
この規定をもとに、「そんな急に辞められても困る」「引継ぎが終わるまでは辞めさせない」といった声も聞かれます。
しかし、従業員が「来月で辞めます」と言ってきたら、会社はそれを拒否できるのでしょうか?
この記事では、2025年現在の法制度をふまえ、「退職の自由」と「就業規則の定め」の関係、さらに実務における対応策までを、労働法と経営の両面からわかりやすく解説します。
民法では「2週間前の申し出」で退職できる
まず基本的な原則から確認しましょう。
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働者はいつでも退職の申入れができ、申入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。
つまり、従業員が退職の意思を会社に伝えたら、最短で2週間後には退職できるのです。
これは、会社の承諾がなくても成立する「一方的な意思表示」であり、法的な効力があります。
就業規則で「3ヵ月前まで」と定める意味はあるのか?
では、就業規則に「退職は3ヵ月前までに申し出ること」と記載してあっても意味がないのかというと、一定の効果はあるといえます。
たとえば、信頼関係のある従業員が、円満退職を希望する場合には、この規定に沿って丁寧にスケジュールを組み、引継ぎも含めて退職を進めてくれるからです。
しかし、問題は「すぐにでも辞めたい」と強く希望する従業員が出てきた場合です。
このようなケースでは、就業規則の定めよりも民法の規定が優先されます。
つまり、就業規則に「3ヵ月前まで」と書かれていたとしても、従業員が退職の申し出をし、2週間に拘れば2週間で契約は終了します。
就業規則で3ヵ月前までの申し出を定めること自体が無効というわけではありませんが、強制力はなく、従業員を法的に拘束することはできないのです。
「引継ぎが終わるまでは辞められない」は通用しない
経営者の中には「せめて引継ぎが終わるまでは辞められては困る」という思いを持つ方も少なくありません。
たしかに、業務の引継ぎは会社運営において極めて重要です。
しかし、これもまた会社側の都合であり、引継ぎの有無によって退職を制限することはできません。
「後任が見つかるまで認めない」「損害賠償を請求する」などの主張もよく見られますが、これらは法的に通用しません。
退職の自由は憲法上も保障されている権利であり、これを過度に制限することは、労働者の基本的権利を侵害する行為と見なされます。
退職前に意図的に業務を妨害する目的で、会社資料や備品を破棄した、情報を漏洩したというような行為があれば損害賠償を請求することもあり得ますが、そもそも退職することだけで損害を与えられたという主張は通らないでしょう。
就業規則は「拘束力」ではなく「共通のルール」
「結局、就業規則なんて意味がないじゃないか」と考えてしまうかもしれませんが、そうではありません。
就業規則は、労使双方が共通のルールのもとで安定的に働くための「ガイドライン」です。
大半の従業員は、迷惑をかけたくないという気持ちから、就業規則の内容に沿って、計画的な退職を申し出てくれます。
就業規則があるからこそ、「退職の申し出は早めに」という意識が社内に共有され、混乱を避けることができます。
重要なのは、そのルールに「法的拘束力がない」ということを理解しつつも、日常的な信頼関係や社内文化の中で機能するよう運用することです。
属人化している業務こそ見直すべき
そもそも「突然辞められたら困る」という状況そのものが、組織としての弱点です。
「この仕事は〇〇さんにしかできない」といった属人化は、退職リスクだけでなく、有給休暇の取得義務や育児休業、長時間労働対策など、すべての人事施策に悪影響を与えます。
突発的な退職があったときに業務が止まるような体制であれば、それは会社としての管理体制の問題です。
業務を洗い出し、マニュアルを整備し、複数の従業員が対応できるような仕組みを整えておくことが、将来的なトラブル回避につながります。
「退職申し出後にすべて有休消化」も拒否できないケースが多い
実務でよくあるのが、「退職日までの2週間、すべて有給休暇を取得したい」と申し出るケースです。
原則として、年次有給休暇は労働者が時季を指定して請求できる権利があり、退職が確定している場合には、会社が時季変更権を行使することも困難です。
つまり、退職日まで出勤してもらいたくても、法律上はその希望を拒否できない場合が多いのです。
このような事態を避けるには、普段から労使の信頼関係を築き、誠実なコミュニケーションを重ねておくことが必要です。トラブルが起こってから対応するのではなく、起こらない仕組みを作ることが経営者の責任です。
まとめ
就業規則に「退職は3ヵ月前までに申し出ること」と書いていても、従業員が一方的に2週間後に辞めると、退職を申し出た場合、法的には2週間後に労働契約は終了します。会社が認めないから辞められない、という状況は成立しません。
それでも、就業規則の規定には意味があります。信頼関係がある職場であれば、多くの従業員は規定に従って円満に退職していきます。問題が起こるのは、すでに会社に不満を抱えている従業員が、トラブル覚悟で辞めようとする場合です。
退職トラブルを防ぐためには、普段から業務の属人化を避け、誰が辞めても回る組織体制を整えること、そして、従業員との信頼関係を丁寧に築いておくことが重要です。退職は突然訪れるものですが、それに備える体制づくりは、今すぐにでも始められます。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
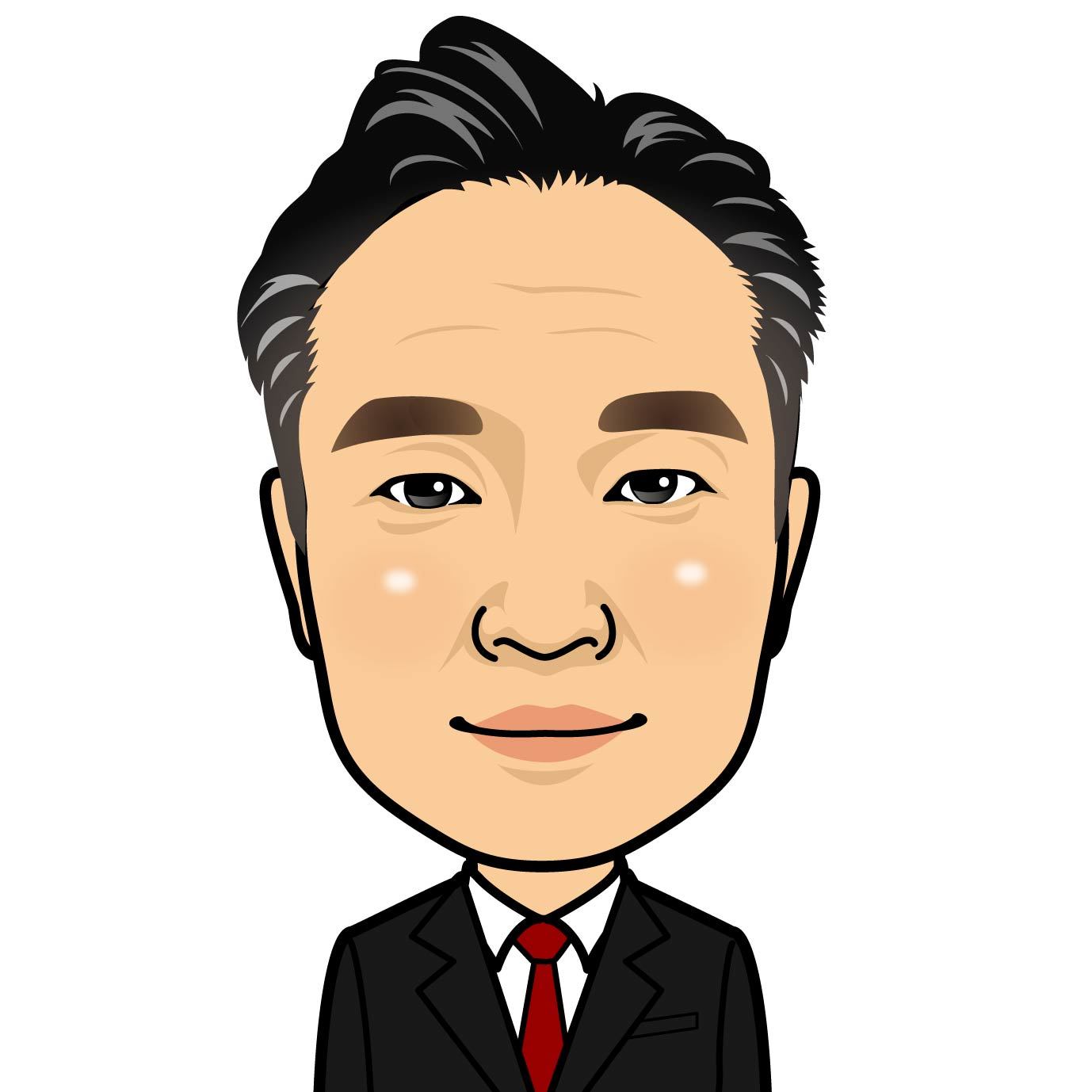
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント
クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計