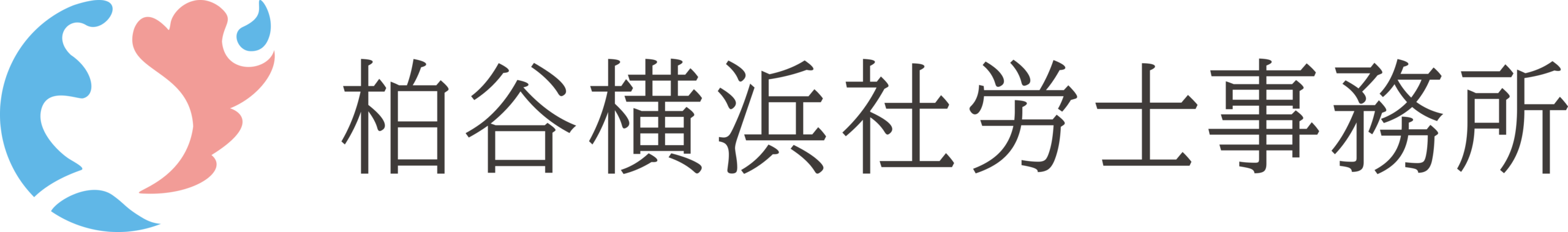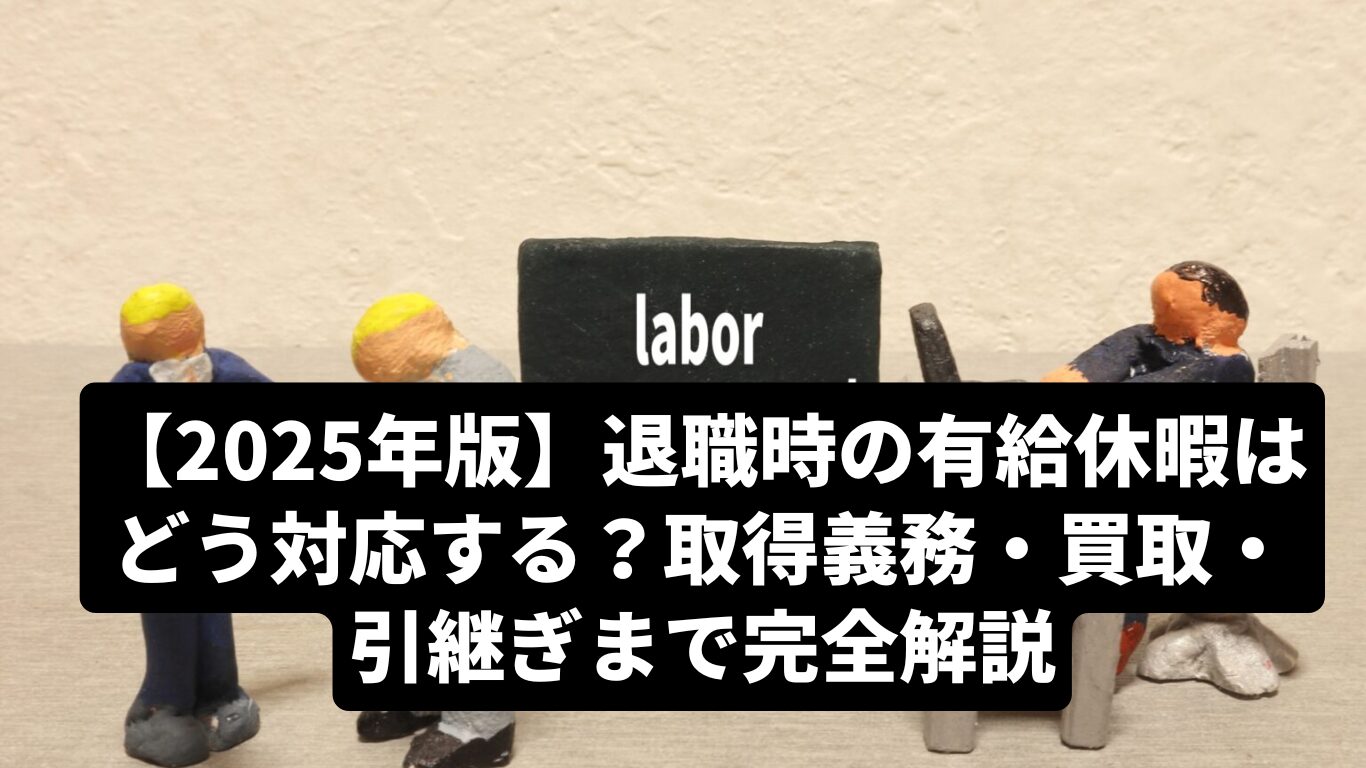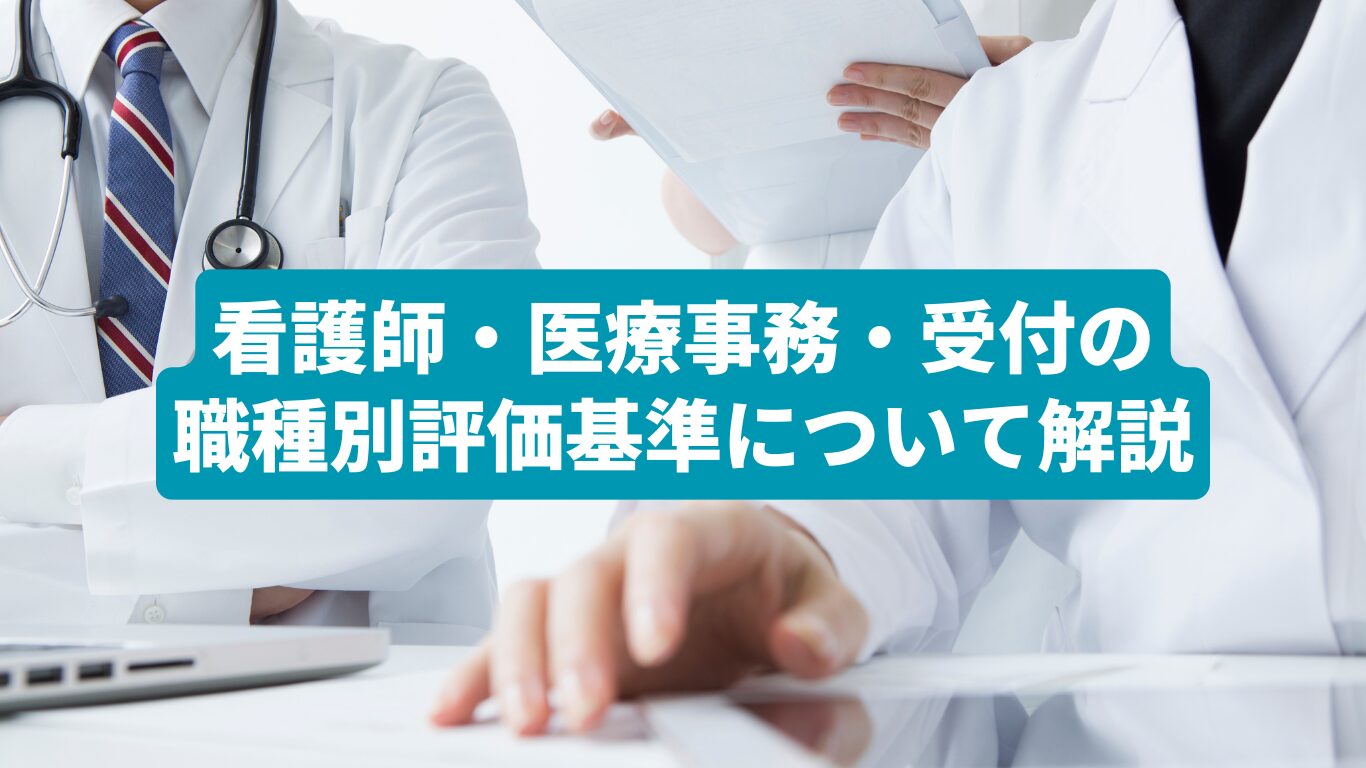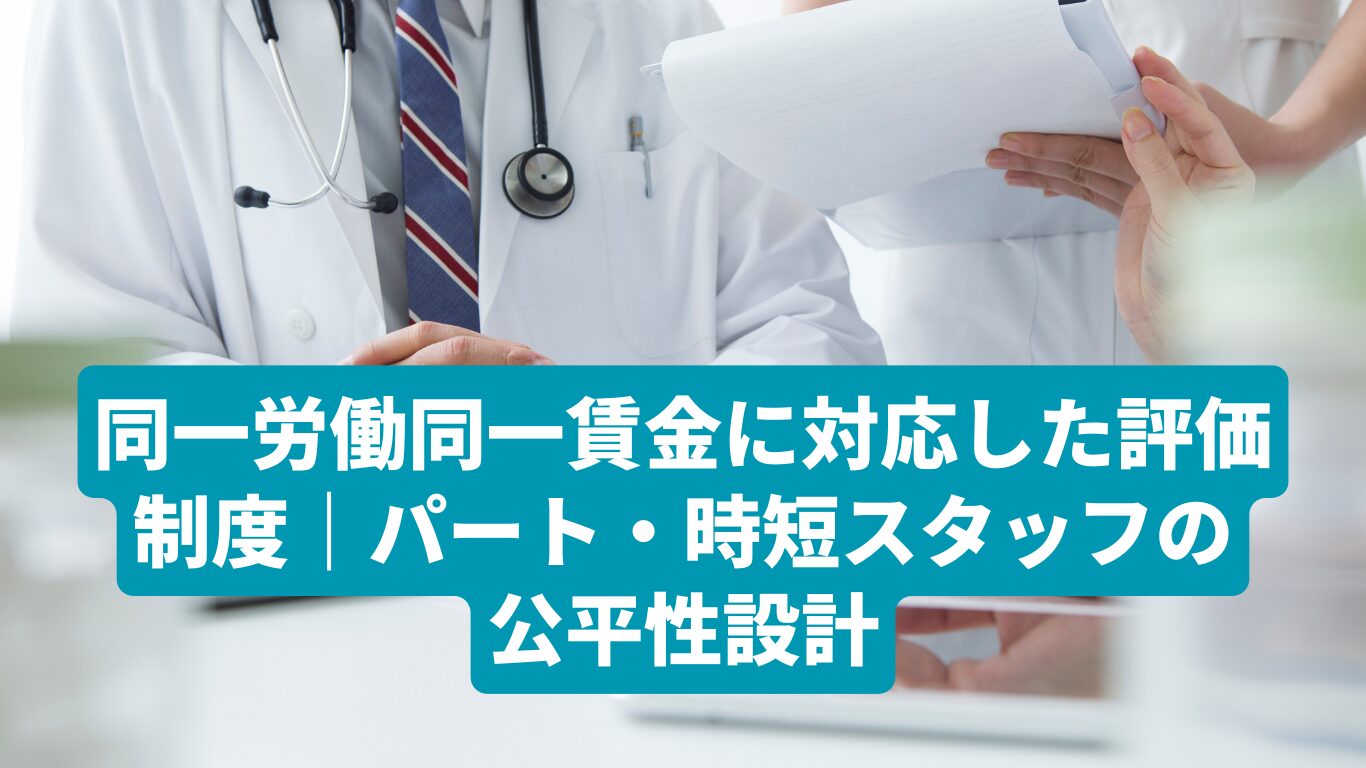2019年4月の法改正により、有給休暇が10日以上付与される労働者には、年間5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となりました。この制度が導入されてから、「退職予定の従業員から『有休をすべて使い切って辞めたい』と言われたが、取らせないといけないのか?」「引継ぎもせずに休みに入られて困る」といった相談が増えています。この記事では、2025年時点での最新情報をもとに、退職時の有給休暇に関する対応を、法的なルールと実務の両面から解説します。
有給休暇は、労働者の請求があれば取得させなければならない
年次有給休暇は、労働基準法第39条により、労働者が希望した時季に取得できることが原則とされています。これを「時季指定権」といいます。
使用者には「時季変更権」という権利があり、事業の正常な運営に支障がある場合には、他の時季に変更することができます。ただし、この時季変更権が認められるのは例外的な場合に限られ、かつ具体的な根拠が必要です。
退職が決まっている従業員に対しては、そもそも退職日という期限があるため、「別の日に変更する」という選択肢が実質的に存在しません。そのため、退職前に希望があれば、有給休暇を付与する必要があります。
退職時の有給休暇は原則すべて消化可能。企業側は拒否できない
退職予定の従業員が「残っている有給をすべて消化したい」と申し出た場合、企業側がそれを拒否することは基本的にできません。
なぜなら、有給休暇は法律で認められた権利であり、退職日までに消化することに何ら制限はないからです。就業規則に「退職時は有休を取れない」などと記載していたとしても、それは無効とされます。
「引継ぎがあるから取らせられない」という事情があっても、それは企業の都合にすぎず、時季変更権も使えない状況であれば、希望通りに有給休暇を与えるしかありません。
有給休暇の買取は原則禁止。ただし退職時は例外的に認められる
有給休暇の目的は、労働者の心身の健康回復や生活の充実を図ることにあります。そのため、使用しない有給休暇を金銭で補填する、いわゆる「買い取り」は原則として認められていません。
しかし、退職が確定している場合で、どうしても有給休暇の全部または一部を取得できないときに限っては、未消化分の買取が認められています。たとえば、最終出勤日までに業務の引継ぎを完了する必要があり、有給休暇の一部が消化できない場合などです。
ただし、買取は企業の義務ではなく任意の対応です。従業員との話し合いのもとで、同意を得たうえで実施することが必要です。
引継ぎとのバランスをどうとるか
有給休暇の消化は従業員の正当な権利ですが、会社としては業務の引継ぎを円滑に行う必要もあります。そこで重要になるのが、双方の話し合いとスケジュール調整です。
実務上は、以下のような方法で対応するケースが多く見られます。
- 退職日から逆算し、有給休暇をすべて消化する前に引継ぎを完了してもらう
- 引継ぎ期間として一部出勤を依頼し、取得できなかった有休は合意のうえで買い取る
- 退職日を少し延ばしてもらい、その間に引継ぎと有給消化の両方を完了させる
いずれにしても、従業員に無理を強いるのではなく、納得感のある調整が重要です。退職者も引継ぎの責任を理解している場合が多いため、冷静に話せば協力を得られるケースがほとんどです。
有給買取の金額は?法的な決まりはないが、実務では1日分の賃金が一般的
退職時の有給休暇の買取については、法律上の金額設定はありません。1日あたりいくらで買い取るかは会社ごとの判断となります。とはいえ、現実には1日分の賃金を基準とするのが一般的です。あまりに低い金額での買い取りを行うと、従業員とのトラブルや社内の不満を招く恐れがあります。
計算方法としては以下のような例が挙げられます。
- 月給制:月給 ÷ 月の所定労働日数
- 日給制:そのままの日給額
- 時給制:所定労働時間 × 時給
買い取り額については、社内ルールとして明文化しておくとトラブル防止になります。
有給休暇の取得義務(年5日)との関係
2019年から始まった年5日の有給休暇取得義務制度では、対象となる労働者に対して、企業が毎年5日以上の有休を取得させる義務を負います。
この取得義務は、退職時にも適用されます。すなわち、退職日までの1年間において、有給を1日も取得していなければ、最低5日分は取得させなければなりません。買取での対応はできず、必ず実際に取得させる必要があります。
ただし、退職時点までにすでに5日以上の有給を取得済みであれば、それ以降の分は未取得でも問題ありません。
就業規則に「退職時の有給は取らせない」と書いてあっても無効
一部の企業では、就業規則に「退職時には有給休暇を取得させない」などと記載していることがありますが、これは法的に無効です。
年次有給休暇は法律に基づく権利であり、労働基準法に反する就業規則の定めは無効となります。実務でこのような条文を運用していた場合、労働者から訴えられる可能性もあります。
就業規則には、引継ぎを促すためのルールや手続き、買取対応に関する記載などを整備しておき、法的に有効な形で運用することが大切です。
まとめ
退職時の有給休暇の取り扱いには、法律上のルールと実務上の配慮の両方が必要です。
- 有給休暇は労働者の希望に応じて取得させなければならない
- 退職が決まっている場合、時季変更権は原則として行使できない
- 有給の買取は原則禁止だが、退職時は例外的に可能
- 引継ぎとの調整は、双方の合意をベースに行うのが望ましい
- 買取額は1日分の賃金が目安。社内ルールとして明文化しておくと良い
- 年5日の取得義務は退職者にも適用されるため、取得状況の確認が必要
これまでの不満が爆発する形での退職では、引継ぎも考慮せず有給休暇を消化して辞めるということが起こりえます。普段からの適切な労務管理が大切です。
また、退職時の対応は、企業の姿勢が問われる場面でもあります。残った社員に悪影響を与えないためにも、正しいルールのもとで、誠実かつ円滑な対応を心がけましょう。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
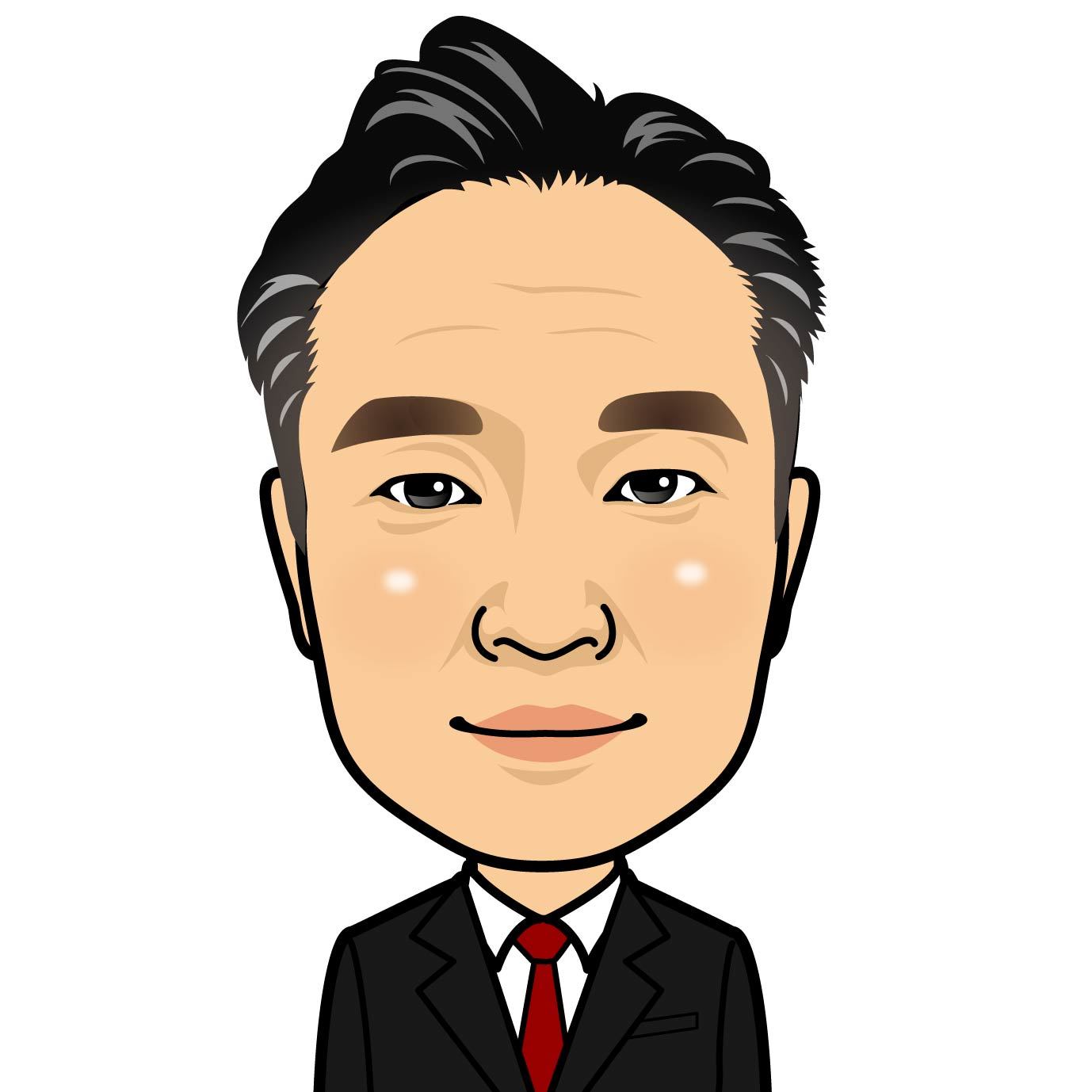
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント
クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計