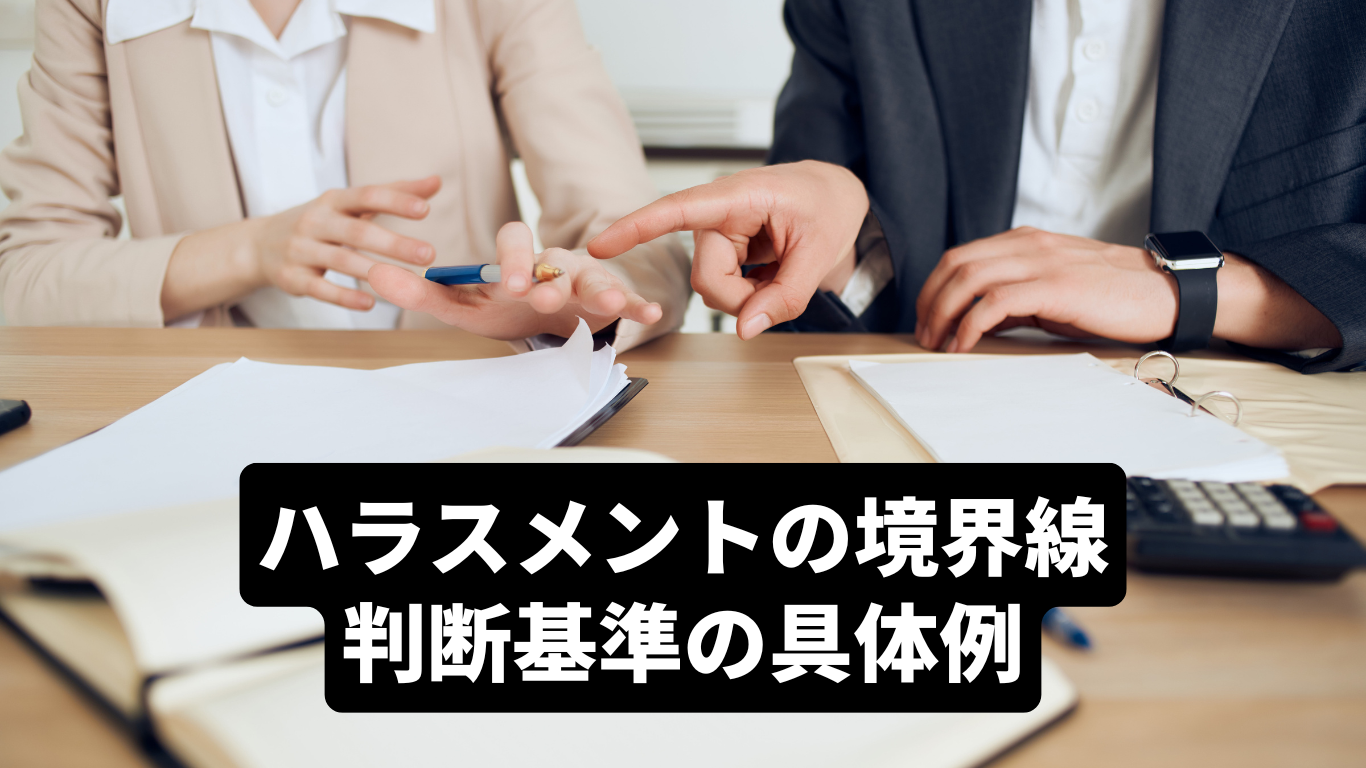年金制度改正法が成立
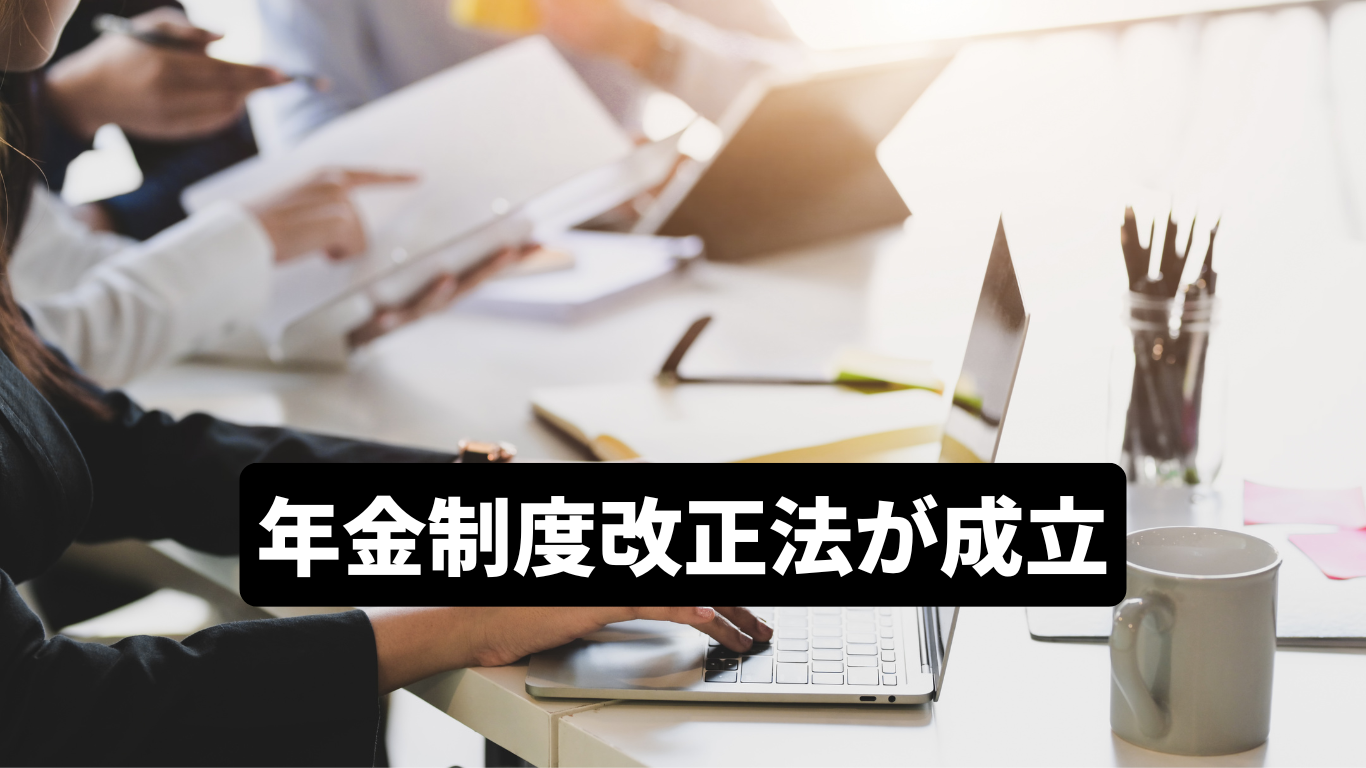
はじめに
年金制度の改正は、社会構造の変化に対応するために定期的に行われています。近年の改正では、少子高齢化の進展や働き方の多様化といった背景を踏まえ、多くの人がより長く働きながら、安心して年金制度を利用できる仕組みへと進化させることが目的となっています。
特に今回の改正では、パート・アルバイトなど非正規雇用の方々にも社会保険の適用が広がり、在職中の年金受給の見直し、さらには確定拠出年金(DC)制度の充実などが含まれており、企業側・従業員側ともに実務への影響が大きい内容となっています。
この記事では、年金制度改正の背景や目的を押さえたうえで、実際の改正ポイントや中小企業への影響、企業として取るべき対応策について、解説していきます。
年金制度改正の背景と目的
少子高齢化と年金財政の逼迫
日本の年金制度は賦課方式を採用しており、現役世代が高齢者の年金を支える仕組みです。ところが、出生率の低下と平均寿命の延伸によって、年金を受給する高齢者の割合が年々増加しています。これにより、制度の持続性が強く問われるようになりました。
年金財政の健全性を維持するには、保険料を支払う側の裾野を広げる必要があります。そのため、これまで社会保険の適用対象外とされていた短時間労働者をカバーすることや、在職中の年金制度を見直して高齢者の就業継続を促すことが、重要な対策と位置付けられました。
働き方の多様化への対応
近年では、正社員だけでなく、パート、契約社員、派遣社員、フリーランスといった多様な働き方が広がっています。従来の制度では、こうした非正規雇用の方々が社会保険に加入できない、あるいは年金額が低くなるという課題がありました。
今回の年金制度改正では、働き方にかかわらず、一定の条件を満たせば社会保険に加入できるようにすることで、雇用形態による不公平感を軽減し、将来的な年金受給の安定にもつながるように設計されています。
生涯現役社会に向けた政策誘導
少子高齢化社会においては、高齢者が元気に働き続ける「生涯現役社会」が重要なテーマです。高齢期においても労働意欲がある方が、就労を継続しやすい環境を整えることが求められています。
そのためには、年金受給と就労の関係を見直す必要があります。在職老齢年金制度の見直しによって、年金をもらいながら働くことが不利益にならないようにする仕組みが導入されました。これは、高齢者の就業促進だけでなく、労働力人口の確保という観点からも重要な施策です。
人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから
改正法の主なポイントと変更内容
パート・アルバイトの社会保険適用拡大
適用対象企業の拡大
これまで短時間労働者の社会保険の加入義務があるのは、常時501人以上の従業員を雇う企業に限られていました。この対象が段階的に拡大され、2022年10月からは101人以上の企業、2024年10月からは51人以上の企業へと対象範囲が広がりました。これにより、中小企業でも一定の条件を満たすパートやアルバイトが社会保険に加入する必要が出てきました。
短時間労働者の社会保険加入要件
社会保険加入の対象となる短時間労働者の条件は、以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(撤廃)
- 勤務期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生ではない
これらの条件を満たせば、パートやアルバイトであっても社会保険の加入が必要となります。
そして今後は、
2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月から10人以上へ、拡大されます。
また月額賃金88,000円以上が撤廃され、いわゆる106万円の壁がなくなったと言われていますが、週20時間以上で働き雇用保険に加入する人は、同時に社会保険も加入するということになります。
在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度の現状と課題
在職老齢年金制度は、年金受給者が就労により一定以上の収入を得ると、年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、年金と賃金の合計が50万円を超えると、年金が減額される仕組みとなっていました。
この制度は、「働くと損をする」と感じさせる要因となり、高齢者の労働参加を妨げる一因ともなっていたため、見直しが強く求められていました。
今回の改正による変更点
改正により、在職老齢年金の支給停止基準額が50万円から62万円に引き上げられます。2026年4月から適用。
これにより、より多くの高齢者が年金を減額されることなく、働きながら年金を受け取ることが可能になります。
働く意欲がある高齢者にとって、就労と年金受給の両立がしやすくなるため、労働市場全体の活性化にもつながると期待されています。
iDeCoの改善
iDeCoの加入年齢上限の引き上げ
iDeCoの加入年齢上限が70歳までに引き上げられます。
これまで国民年金の被保険者は60歳まで、会社員などの第2号被保険者は65歳までの加入でしたが、一律70歳まで加入可能となります。
働き方にかかわらず老後資金を確保できる環境を整備することは、社会的な公平性を高めるうえでも重要です。
企業にとっては制度整備に一定の手間がかかる一方、福利厚生の充実や従業員の定着率向上につながる可能性もあります。
その他(厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ)
厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う標準報酬月額の上限が、月65万円から75万円に引き上げられます。
2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円。
一般的には部長や役員クラスの給料額かと思いますが、給料の高い人の保険料は段階的に上がってしまいます。
給料計算時に注意が必要です。
中小企業への影響とは
社会保険加入対象者の増加
今回の年金制度改正により、これまで社会保険の適用対象外だったパートやアルバイトなどの短時間労働者のうち、一定の条件を満たす方も加入対象となりました。この変更により、中小企業でも対象となる従業員が増える可能性が高まっています。
これまでは、厚生年金や健康保険の加入義務がなかった労働者についても、今後は要件を満たせば適用対象になります。
対象者が増えることで、企業には保険料の事業主負担が増えるという金銭的負担も発生します。これまで非正規従業員のコスト面での利点を重視していた中小企業にとっては、経営へのインパクトが小さくありません。
就業規則や雇用契約の見直し必要性
社会保険の適用範囲が拡大されると、それに対応した就業規則や雇用契約書の整備が求められます。たとえば、雇用形態によって手当や福利厚生の内容が異なる場合、社会保険加入を前提とした内容に変更が必要になるケースもあります。
さらに、加入要件に該当する従業員への説明責任も発生します。これまで社会保険に加入していなかった層に対して、どのような影響があるのか、保険料負担や給付の内容をきちんと理解してもらう必要があります。
事務負担とコスト増加の可能性
社会保険の適用範囲が広がるということは、事務手続きの量も増えることを意味します。新たに加入対象となる従業員についての届出、保険料の計算と納付、月額変更届や算定基礎届の作成など、労務担当者にかかる負担は増大します。
また、これに伴って外部の社会保険労務士に依頼するケースも増えるかもしれませんが、委託費用もコストとして考慮が必要です。
企業負担分の社会保険料の増加により、経営に直接影響を与える可能性もあります。特に、薄利で運営している中小企業にとっては、加入義務がある従業員数のわずかな増加が経営に与える影響は決して小さくありません。
そのため、経営者としては事前に制度の改正内容をしっかりと把握し、シミュレーションを行った上で、早めに対策を講じることが大切です。
人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから
今後の展望と企業が取るべき対応策
労務管理体制の再点検
年金制度の改正を受けて、企業には従来の労務管理体制を見直す必要があります。特にパート・アルバイトを含めた非正規雇用者の増加に対応するためには、勤怠管理、就業規則、雇用契約の整備が求められます。
例えば、これまで社会保険の対象外だった従業員が新たに加入対象となる場合、勤務時間の管理や契約条件の再設定が必要になります。制度への対応が遅れると、適用漏れや法令違反につながる可能性もありますので、現行体制のチェックと必要な修正を行うことが大切です。
社会保険の適用漏れ防止策
適用拡大により、対象者を見落とすリスクも高まります。特に「週20時間以上」の条件に該当する短時間労働者が該当するかどうかは、毎月の変動や雇用形態の変更により判断が難しくなるケースもあります。
このようなリスクを防ぐためには、定期的に対象者の洗い出しを行う仕組みを導入することが有効です。人事システムの活用やチェックリストの作成など、管理方法をルール化しておくと安心です。社会保険労務士への相談も一つの手段といえます。
従業員への制度周知と説明方法
制度改正があるたびに従業員からの質問や誤解も生じがちです。特に社会保険の加入対象となったパートの方にとっては、保険料の負担や手続きについて不安を抱くことも少なくありません。
こうした不安を解消するためには、丁寧な説明と情報提供が欠かせません。説明会の開催、資料配布などを通じて、制度の背景やメリット・デメリットをわかりやすく伝えることが重要です。正しい情報を提供することで、従業員の納得と協力が得られやすくなります。
労務戦略としての長期的な備え
今回の改正は一時的な対応ではなく、長期的に続く社会環境の変化を踏まえたものです。企業としても、今後さらに進む高齢化や労働人口の減少に対応するため、労務戦略を中長期的な視点で見直す必要があります。
例えば、65歳以降の継続雇用制度の整備や、柔軟な働き方への対応(短時間正社員制度など)を進めることも求められるでしょう。人材の定着やモチベーション向上といった観点からも、制度改正を前向きな機会と捉えることが企業の成長につながります。
社会保険労務士のサポートで安心の労務管理を
就業規則・賃金規程の見直し支援
年金制度の改正により、企業は就業規則や賃金規程の見直しが求められる場面が増えています。特にパート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険適用が拡大されることで、これまで対象外だった従業員にも制度が及ぶようになりました。
その結果、勤務時間や日数に応じた賃金体系の整備、社会保険加入に関する記述の追加、在職老齢年金制度への対応を含めた記載など、就業規則の内容を現状に即したものへと見直す必要があります。
こうした法改正に対応するには、労働法や社会保険制度に精通した専門家の支援が有効です。社会保険労務士は、法改正の内容を踏まえた実務的な就業規則の修正案を提示することが可能であり、従業員への周知や運用上の助言も行います。これにより、労使双方のトラブル防止にもつながります。
社会保険手続き代行と相談業務
改正によって社会保険の適用対象者が増加すると、企業の実務負担も大きくなります。特に、中小企業にとっては、保険加入・脱退の手続きや標準報酬月額の決定、年金事務所とのやり取りなどに多くの時間を取られることもあるでしょう。
こうした事務手続きに関しても、社会保険労務士のサポートを活用することで、煩雑な作業を効率化できます。特に電子申請の対応や定期的な書類提出など、ミスが許されない作業においては、専門家の関与によって業務の正確性が確保されます。
また、今後の制度変更を見据えたアドバイスを受けることも可能です。たとえば、パートタイマーの就労時間が拡大した場合の対応、将来的な就業規則の変更の必要性、個別従業員からの質問対応における方針の相談など、実務に即した支援を得られます。
社会保険労務士は、制度運用の「現場」を理解しているパートナーとして、企業の労務リスクを未然に防ぎ、安定した経営を支える存在となります。
まとめ
今回の年金制度改正は、高齢化社会に対応した持続可能な年金制度への転換を目的としており、中小企業にとっても無関係ではありません。パート・アルバイトへの社会保険適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、iDeCoの改善といった変更点は、企業の人事・労務管理に直接的な影響をもたらします。
特に、社会保険加入対象者の増加によるコストや事務負担は、中小企業にとって無視できない課題です。しかし一方で、適切に対応すれば、従業員の福利厚生の充実や人材の定着につながる可能性も秘めています。
今後は、労務管理体制を見直し、制度変更に対応した就業規則の整備や、従業員への丁寧な説明などが重要になります。社会保険労務士などの専門家と連携しながら、自社にとって最適な対応策を講じていくことが、変化の時代を乗り切る鍵となります。
働き方が多様化し、従業員の意識も変わる中、制度改正をチャンスと捉え、より柔軟かつ安心できる職場環境の整備を進めていきましょう。
中小企業の経営者様必見!!
人事労務に関する役立つ資料が無料でダウンロードできます!
日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
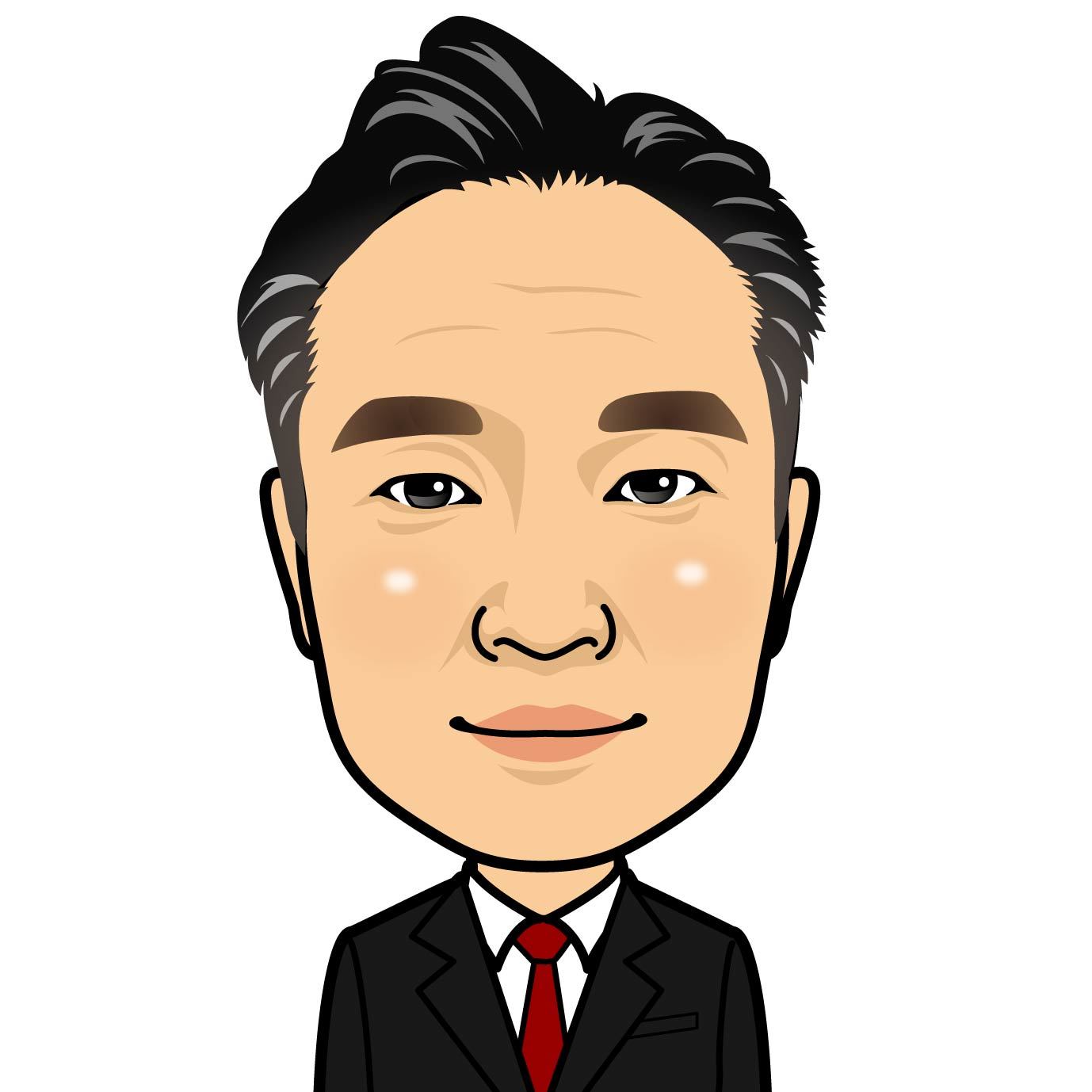
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
最新の投稿
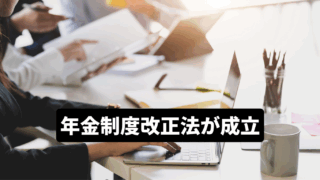 年金2025年7月12日年金制度改正法が成立
年金2025年7月12日年金制度改正法が成立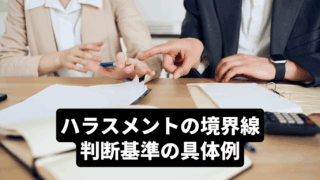 労務管理2025年6月16日ハラスメントの境界線、判断基準の具体例
労務管理2025年6月16日ハラスメントの境界線、判断基準の具体例 労務管理2025年4月21日解雇と退職勧奨、解雇は危険
労務管理2025年4月21日解雇と退職勧奨、解雇は危険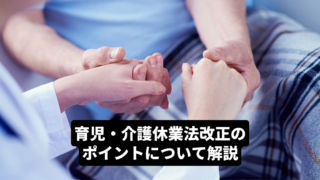 労務管理2025年3月24日育児・介護休業法改正のポイントについて解説
労務管理2025年3月24日育児・介護休業法改正のポイントについて解説