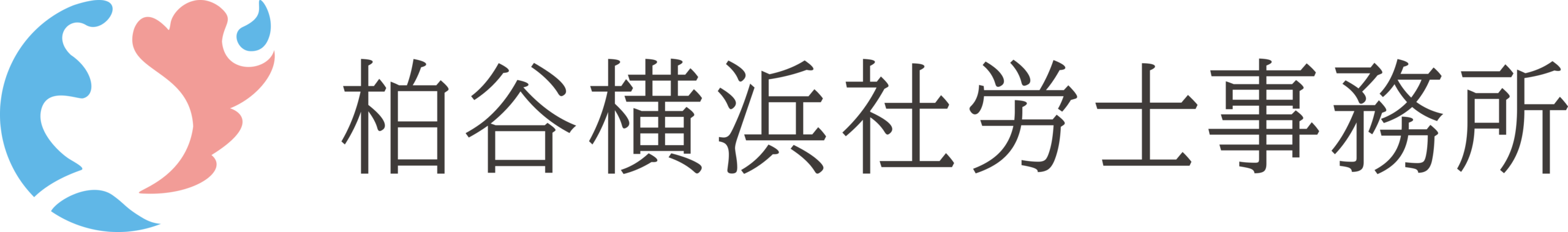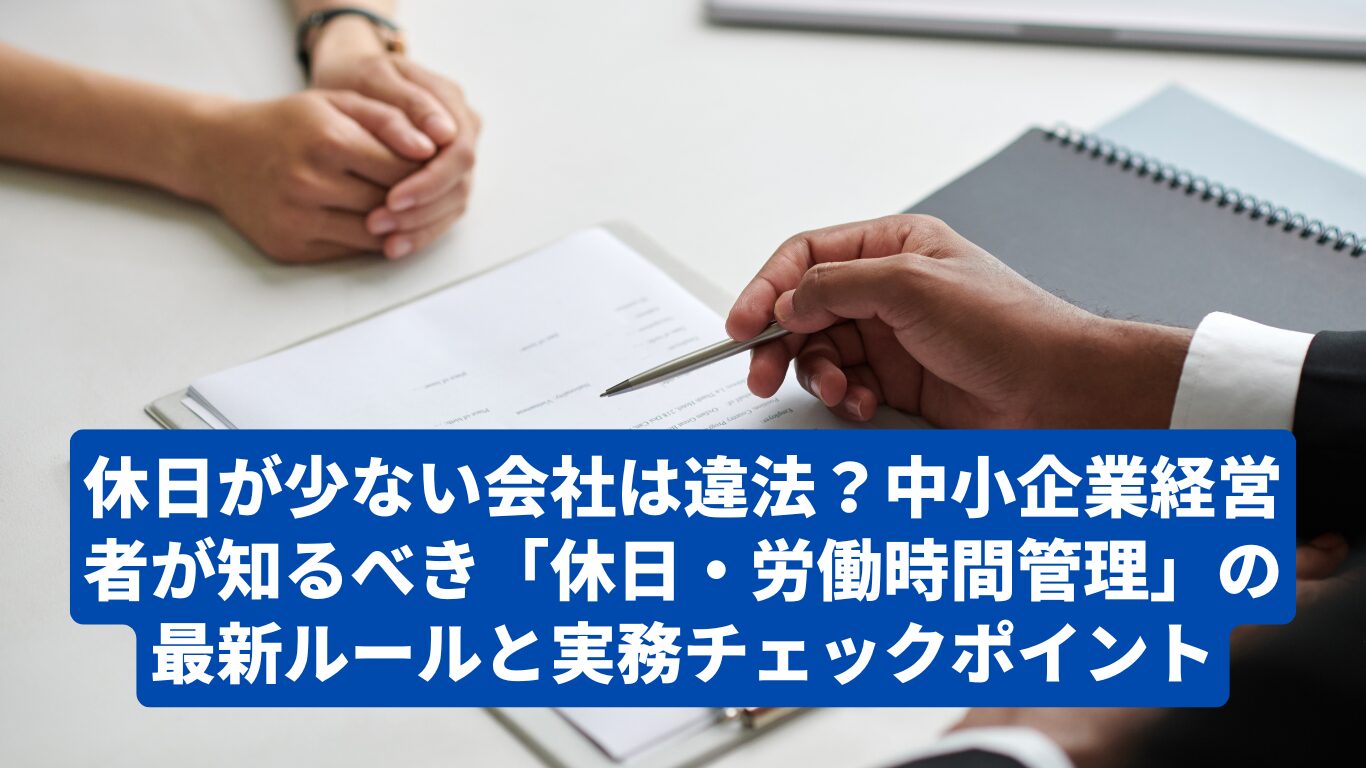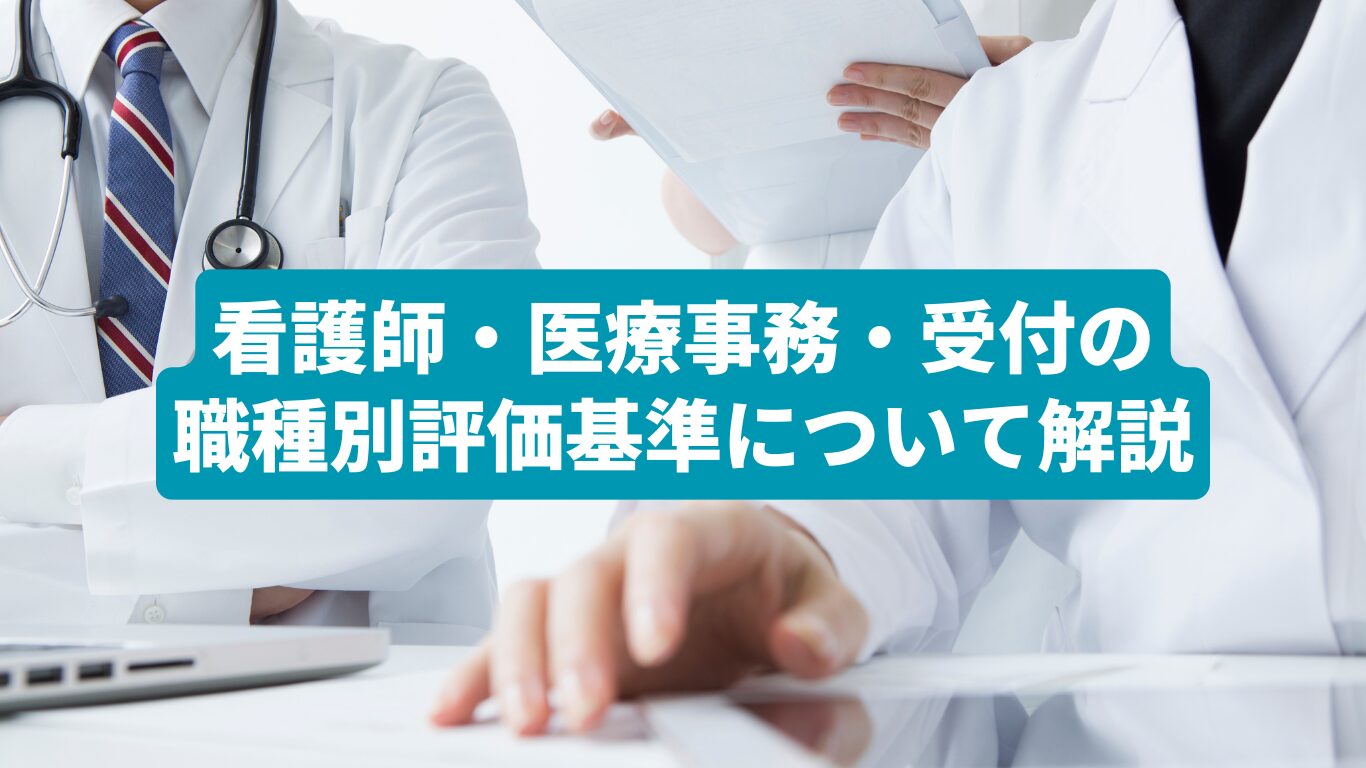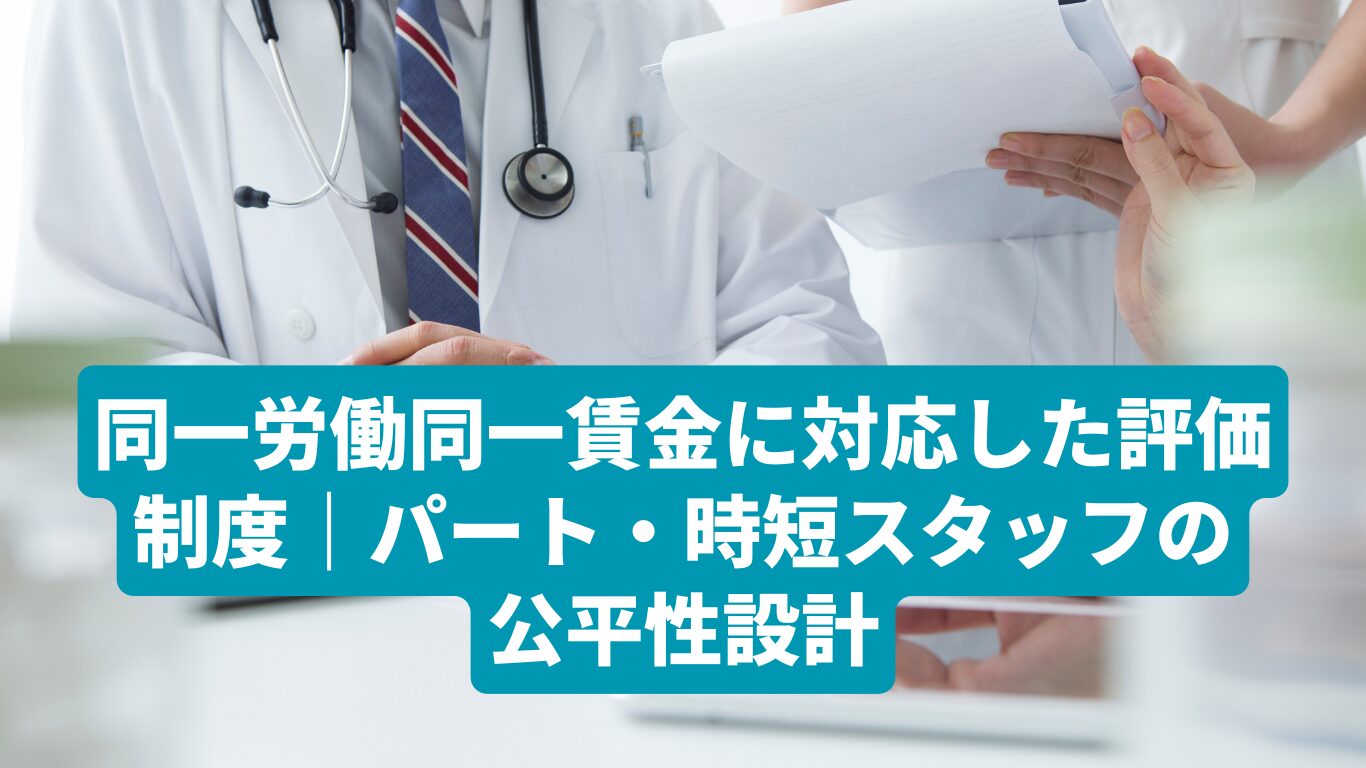はじめに
「週に1日しか休みがないのは違法では?」という疑問を持つ従業員や経営者は少なくありません。特に中小企業では、業務の都合上、週休2日を確保することが難しい場合もあります。法律上はどのように定められているのか、そして実務上どのように運用すべきなのかを理解していないと、知らぬ間に違法状態に陥る可能性があります。本記事では、労働基準法における休日・労働時間の基本を踏まえながら、2025年時点の最新情報をもとに、中小企業経営者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
なぜ「休日の少なさ」が経営課題になるのか
採用・定着率に直結する要素
休日が少ない職場は、若手を中心に応募が集まりにくく、定着率も下がる傾向があります。求人票で「週休1日」と明記すると、その時点で応募数が半減することも珍しくありません。労基法上は合法であっても、求職者の感覚では「ブラック企業」という印象を持たれる恐れがあります。
生産性と健康リスクの関係
休日が少ない勤務体系では、疲労が蓄積し、集中力や判断力の低下を招きやすくなります。結果的にミスが増え、業務効率が下がることも多いです。経営者としては、休日数を「コスト」としてではなく、「生産性を守る投資」として捉えることが重要です。
法令遵守だけでは不十分な時代
法定基準を満たしていれば問題ないという考え方は、今の採用市場では通用しにくくなっています。労務リスクの回避に加え、従業員が安心して働ける環境を整えることが、経営戦略の一部といえます。
労働基準法における休日の基本ルール
法定休日とは
労働基準法第35条では、使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」を与えなければならないと定めています。つまり、週1日の休日があれば、法律上は適法です。
法定労働時間との関係
法定労働時間は1日8時間、週40時間が上限です。例えば、「平日7時間×5日+土曜5時間」で合計40時間となる勤務は合法です。ただし、1日8時間や週40時間を超える場合は「時間外労働」となり、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要になります。
所定休日との違い
会社が独自に定めた休日を「所定休日」といいます。法定休日とは別に、企業ごとに設定可能です。例えば、法定休日を日曜日、所定休日を土曜日と設定して週休2日にしているケースが一般的です。
所定労働時間と法定労働時間の違いを理解する
所定労働時間の定義
所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書で定めた通常の勤務時間を指します。たとえば「9時から18時(休憩1時間)」などが該当します。この時間を基準として給与計算や残業の判定を行うため、明確に定義しておくことが重要です。
法定労働時間を超えた労働
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合には、必ず36協定の届け出が必要です。届出がないまま残業をさせると、違法状態となり、労働基準監督署が発見したら必ず是正勧告を受けます。
実務上の注意点
従業員10人以上の会社では、就業規則の作成と届出が義務付けられています。所定労働時間や休日のルールが明文化されていない場合は、まず就業規則の整備が必要です。
週1日休みでも合法な勤務パターンの具体例
医療・福祉業界のケース
医療機関や介護施設では、日曜のみが休日であるケースも多くあります。たとえば「月火水金8時間、木土4時間、日曜休み」であれば、週40時間以内に収まり適法です。このような勤務体系は「シフト制」「変形労働時間制」を併用することで柔軟に運用できます。
製造業・サービス業での運用例
繁忙期や受注量の増減に応じて、週1回の休日しか取れない週が発生する場合があります。その場合も、4週間を平均して4日以上の休日が確保されていれば違法ではありません。1ヵ月単位の変形労働時間制を導入することで、繁忙・閑散期に対応できます。
適法でもリスクは残る
法的には問題がなくても、従業員の負担が大きくなると、離職やメンタル不調の原因になります。経営者は、適法であるかどうかに加え、従業員の健康とワークライフバランスを考慮した運用を意識することが求められます。
残業と休日出勤の割増賃金
基本の割増率
労働基準法では、法定労働時間を超える残業には25%以上、法定休日の労働には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。深夜労働(22時〜翌5時)に対しては25%が上乗せされます。
60時間超の残業はさらに高率に
2023年4月からは、中小企業にも「月60時間超の時間外労働に対する割増率50%」が適用されています。大企業だけでなく中小企業も対象となったため、長時間労働を前提とした運用は通用しなくなっています。
適正な給与計算と管理の重要性
勤怠管理が曖昧な状態では、未払い残業代が発生しやすくなります。後から従業員に請求されると、3年分の未払い賃金を遡って支払う義務が生じる可能性があります。勤怠管理システムやタイムカードの導入で、正確な記録を残すことが不可欠です。
働き方改革と休日制度の最新動向
勤務間インターバル制度の義務化検討
国は、労働時間の上限規制だけでなく「勤務間インターバル制度(休息時間の確保)」の導入を推進しています。一定の休息時間を設けることで、過労防止と健康維持を図る狙いがあります。
年次有給休暇の取得義務化
2019年以降、年5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されています。週1日しか休めない職場では、有給休暇も取りづらい傾向にあるため、制度運用上の工夫が求められます。
「休み方改革」への流れ
単に休日数を増やすだけでなく、「休み方」を工夫する動きも広がっています。リフレッシュ休暇や連続休暇制度、フレックスタイム制などを組み合わせることで、柔軟な働き方が可能になります。
中小企業が取るべき労務管理のポイント
就業規則の整備と運用
休日・労働時間の取り決めは、就業規則に明記することが基本です。「法定休日」「所定休日」「変形労働時間制の対象期間」などを具体的に定義し、実際の勤務シフトと矛盾がないように整備します。
勤怠管理の仕組み化
紙のタイムカードや自己申告に頼る運用は、誤差が生じやすくトラブルの原因になります。クラウド勤怠システムを導入することで、出退勤の自動記録や残業時間の自動計算が可能になり、管理コストを削減できます。
休日取得のルール明文化
「月に何日休めるのか」「休日出勤を命じる場合の手続き」「代休や振替休日の取り扱い」など、休日関連のルールを明確にしておくことで、後のトラブルを防げます。
魅力ある職場づくりと休日制度の関係
年間休日の“印象値”を意識する
求人票では「年間休日105日未満」は少ない印象を与えます。可能であれば年間休日110日以上を確保し、採用活動での競争力を高めることが望ましいです。
柔軟な休暇制度の導入
短時間勤務や時間単位の有給休暇などを導入すると、従業員の満足度が高まります。制度を整えるだけでなく、実際に取得できる環境づくりも重要です。
「休みやすい職場」が信頼につながる
休みが取りやすい職場は、従業員が長く働きたいと感じる要素の一つです。経営者が率先して有給を取得することで、休暇取得が文化として根づきやすくなります。
経営者が確認すべきチェックリスト
- 就業規則に休日・労働時間の定義が明記されているか
- 36協定が適切に届出・運用されているか
- 法定休日を毎週1回以上確保しているか
- 勤怠管理が正確に行われているか
- 割増賃金を正しく支払っているか
- 有給休暇の取得率を把握しているか
- 年間休日が採用市場の平均と乖離していないか
- 休日出勤・振替休日のルールが明文化されているか
- 従業員の健康状態・残業時間をモニタリングしているか
- 働き方改革関連の最新法令に対応しているか
まとめ
休日が少ない勤務体系は、必ずしも違法ではありません。ただし、法令上の最低基準を満たすだけでは、現代の労働環境には適していません。中小企業経営者は「合法かどうか」だけでなく、「従業員が健康で長く働けるか」「採用・定着に不利ではないか」という視点で休日制度を見直す必要があります。労働時間管理と休暇設計を整えることは、労務リスクの軽減と企業の信頼向上の両立につながります。経営資源としての「人」を守るために、休日制度の整備を経営課題の一つとして位置づけていくことが重要です。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
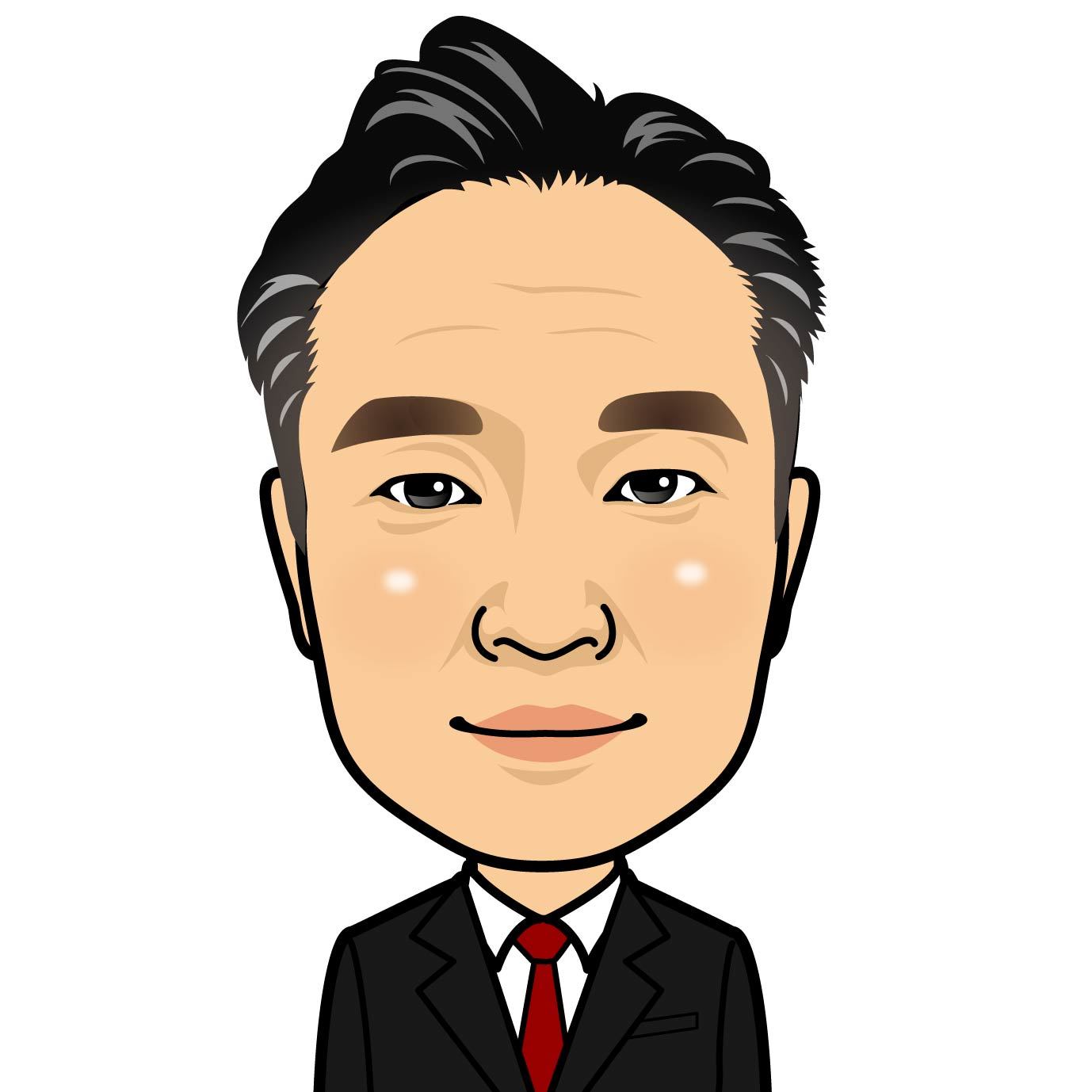
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント
クリニック2026年2月6日シフト制・時短・パートが多い職場の評価運用|勤怠の差を公平に織り込む実務ポイント クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計