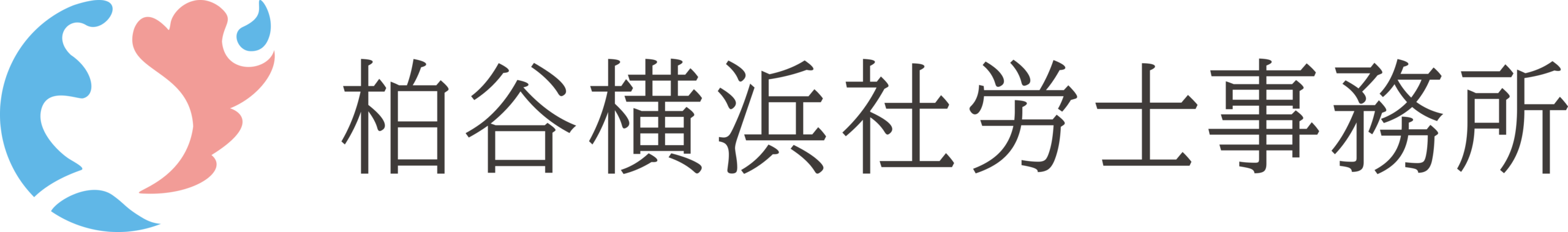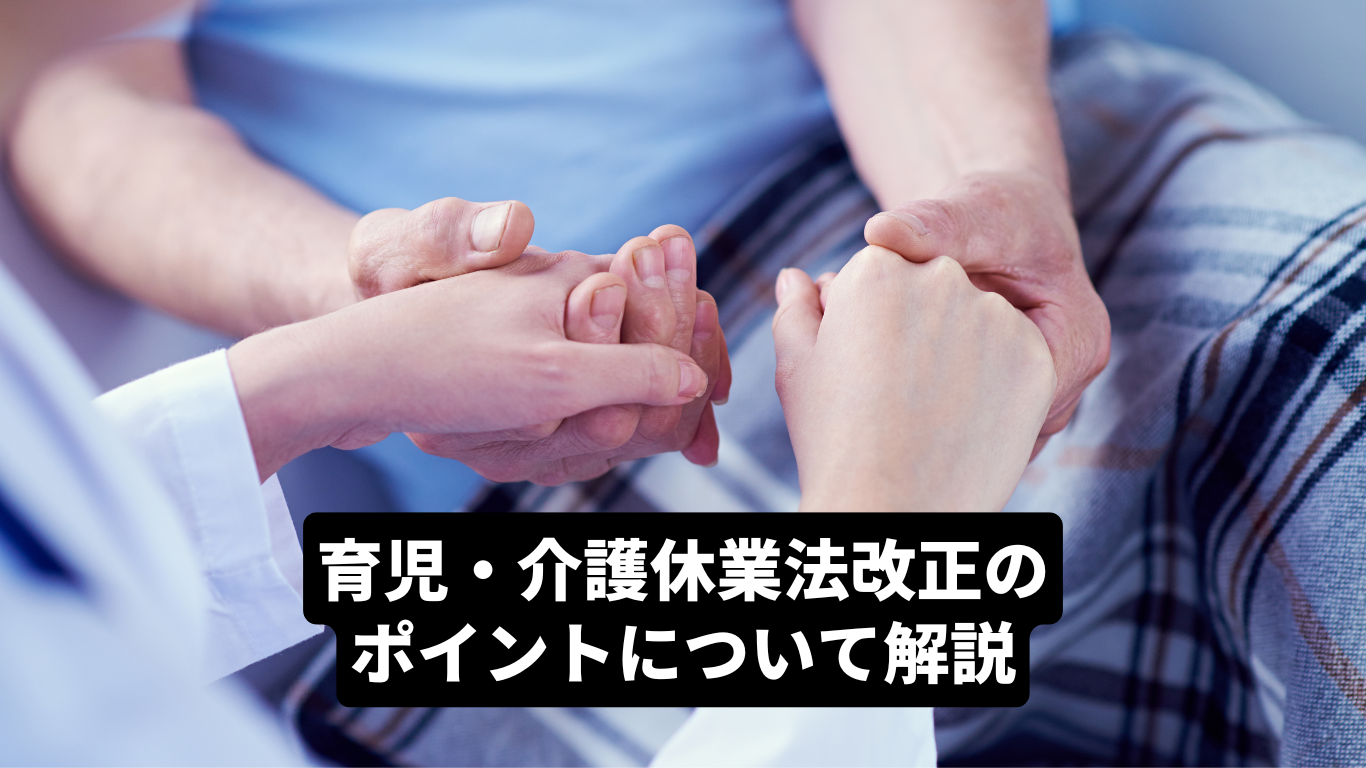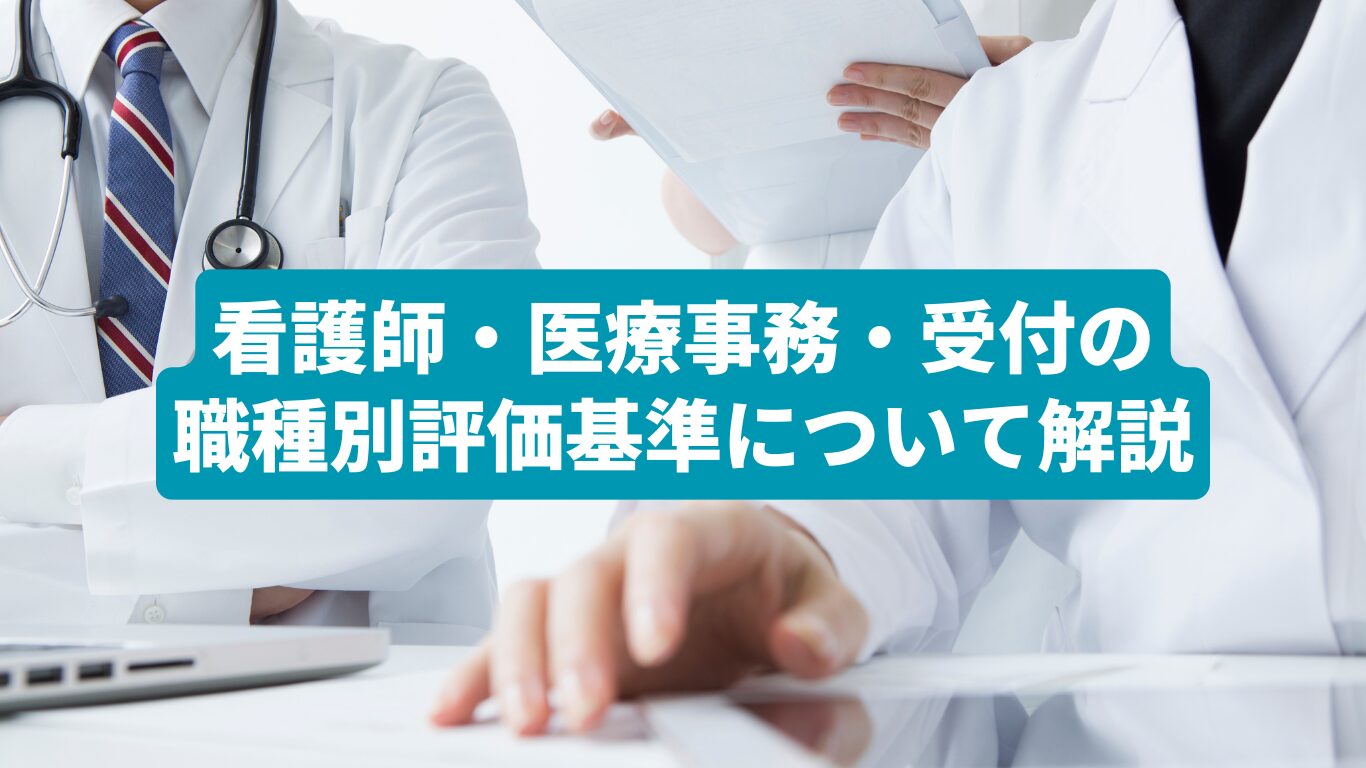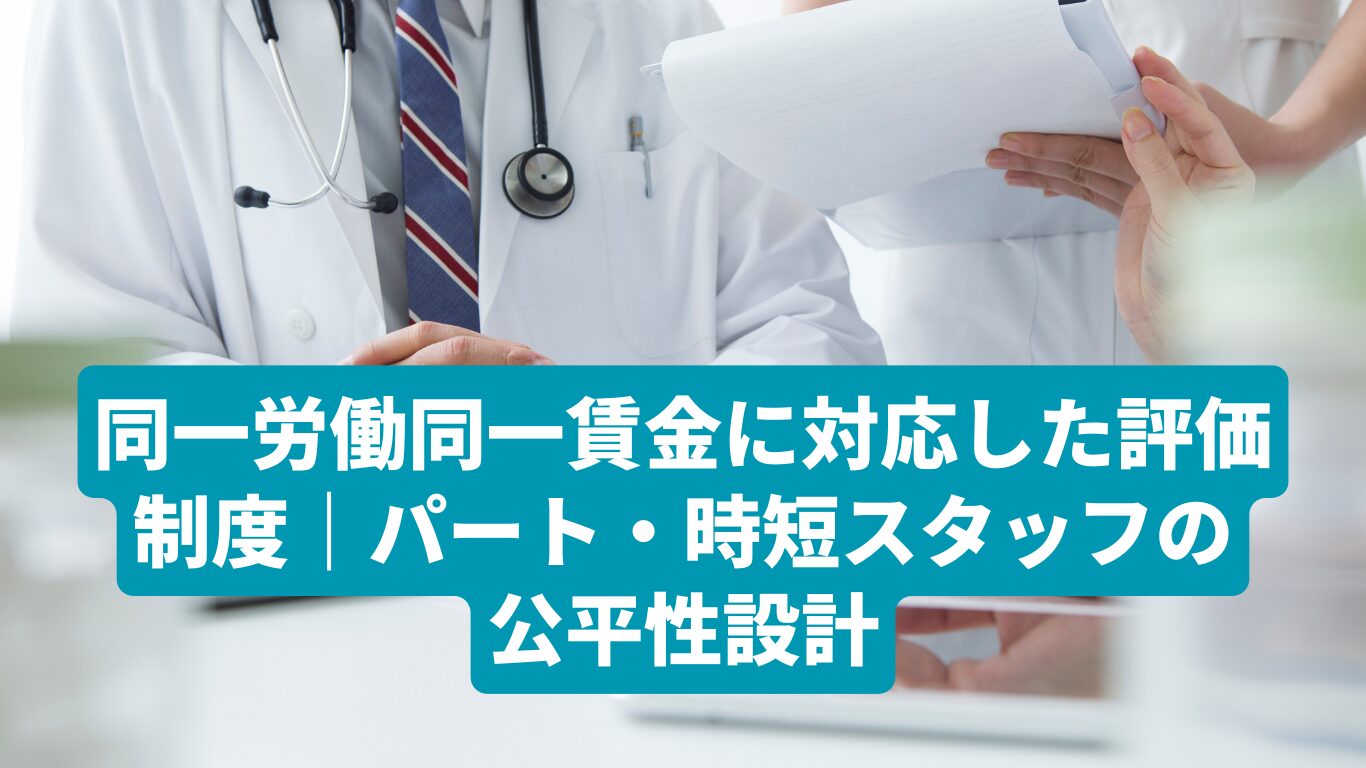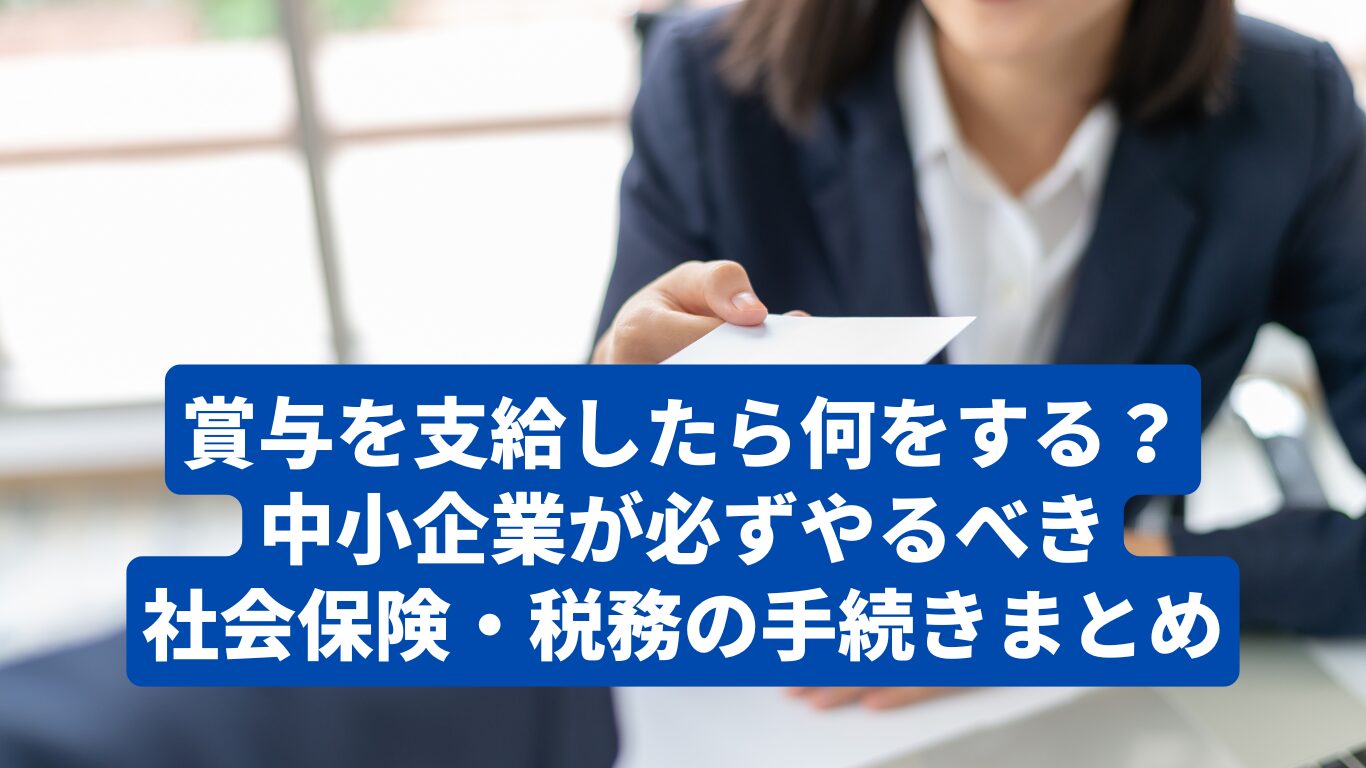はじめに
2025年4月1日から「育児・介護休業法」が改正されます。今回の改正は、より一層、働く人が育児や介護をしながら安心して仕事を続けられる職場環境を整備することを目的としています。この記事では、特に中小企業の経営者や人事担当者向けに、法改正の内容や実務で必要となる対応についてまとめました。改正ポイントをしっかり理解し、スムーズな対応に役立ててください。
育児・介護休業法改正のポイントと具体的対応
子の看護休暇が使いやすくなります
子の看護休暇は名称が「子の看護等休暇」に変わります。対象年齢が従来の「小学校入学前」から「小学校3年生終了まで」に拡大されました。また、感染症による学級閉鎖や入園・入学式、卒園式などの行事参加も新たな取得理由として認められます。また、継続雇用期間が6か月未満の従業員の取得制限が撤廃され、より多くの人が取得できるようになります。
所定外労働(残業)の制限の対象範囲が広がります
従来は3歳未満の子どもを育てる従業員に限られていた所定外労働(残業)の制限の対象が、小学校就学前の子どもを持つ従業員まで広がります。企業は、対象となる従業員が請求した場合、所定外労働(残業)の制限に対応する義務があります。
短時間勤務の代わりにテレワークが選べるようになります
3歳未満の子どもを持つ従業員に対し、短時間勤務が難しい場合には代替措置としてテレワーク制度の導入が可能となります。自社の業務状況を踏まえ、可能であれば、テレワークを選択肢に加えることができます。
育児休業の取得状況公表の義務化対象企業が拡大します
現在は従業員1,000人超の企業が取得状況公表の対象でしたが、2025年4月からは従業員300人超の企業まで義務化が拡大されます。公表する内容は、男性の育児休業取得率などで、企業のホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」などで公開します。
介護休暇の取得がより身近になります
介護休暇についても、継続雇用期間が6か月未満の従業員への取得制限が撤廃され、雇用期間に関係なく取得可能になります。多様な雇用形態で働く従業員がより介護休暇を取得しやすくなるでしょう。
介護離職を防ぐため企業が取り組むべきこと
介護休業や介護両立支援の制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、企業は次のいずれかの措置を講じる必要があります、
①介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施
②介護休業・介護両立支援制度に関する相談窓口の設置
③自社の従業員の介護休業取得・・介護両立支援制度の利用の事例の収集・提供
④自社の従業員への介護休業取得・・介護両立支援制度の利用促進に関する方針の周知
介護に直面した従業員へのサポートが義務化されます
従業員から介護について相談を受けた場合、企業は介護休業や介護両立支援制度の内容を個別に説明し、従業員の希望を確認する必要があります。具体的には、面談(オンライン可)、書面、FAX、電子メールなどで対応可能です。
介護に備えた早期の情報提供が求められます
企業は従業員が40歳を迎える年度を目安に、介護休業制度や介護保険制度に関する情報提供を義務付けられます。これにより、従業員が介護に直面する前に制度を理解し、事前に準備することが可能になります。
ただし、40歳を迎える年度をピックアップするのは大変ですし、全従業員に向けたアナウンスで対応することも予想されます。
育児期間の柔軟な働き方を支援する措置が義務化されます
企業は「柔軟な働き方」の制度を整備する必要があります(2025年10月施行)
3歳から小学校入学前の子どもを持つ従業員に対して、企業は以下の5つの制度から2つ以上を選択し、従業員がその中から1つを選べるようにしなければなりません。
- 始業・終業時刻の柔軟化(フレックスタイムや時差出勤)
- テレワーク(月10日以上、時間単位で取得可)
- 保育施設の設置やベビーシッターの手配などの支援
- 養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位で取得可)
- 短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)
従業員個人への意向確認と配慮が求められます
企業は従業員本人やその配偶者が妊娠・出産したとき、また子どもが3歳を迎えるまでの間に、勤務時間や勤務地、業務量などについて従業員の希望を個別に確認する必要があります。その後、企業の事情を踏まえて、希望に沿った配慮や調整を行います。
制度導入のための準備と注意点
新制度を導入する際には、就業規則の改定が必須です。規則改定の際には従業員代表の意見を聴き、内容を労働基準監督署へ届け出る必要があります。また、制度導入後も従業員への周知や定期的な見直しを行い、運用が適切かどうかを確認していきましょう。
まとめ
今回の育児・介護休業法の改正は、企業にとっては対応が求められるポイントが多くありますが、一方で従業員が働きやすい環境を作るための良い機会でもあります。安心して働き続けられる制度の整備は、従業員の満足度や企業の競争力向上にもつながるでしょう。しっかりと準備を進めていきましょう。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
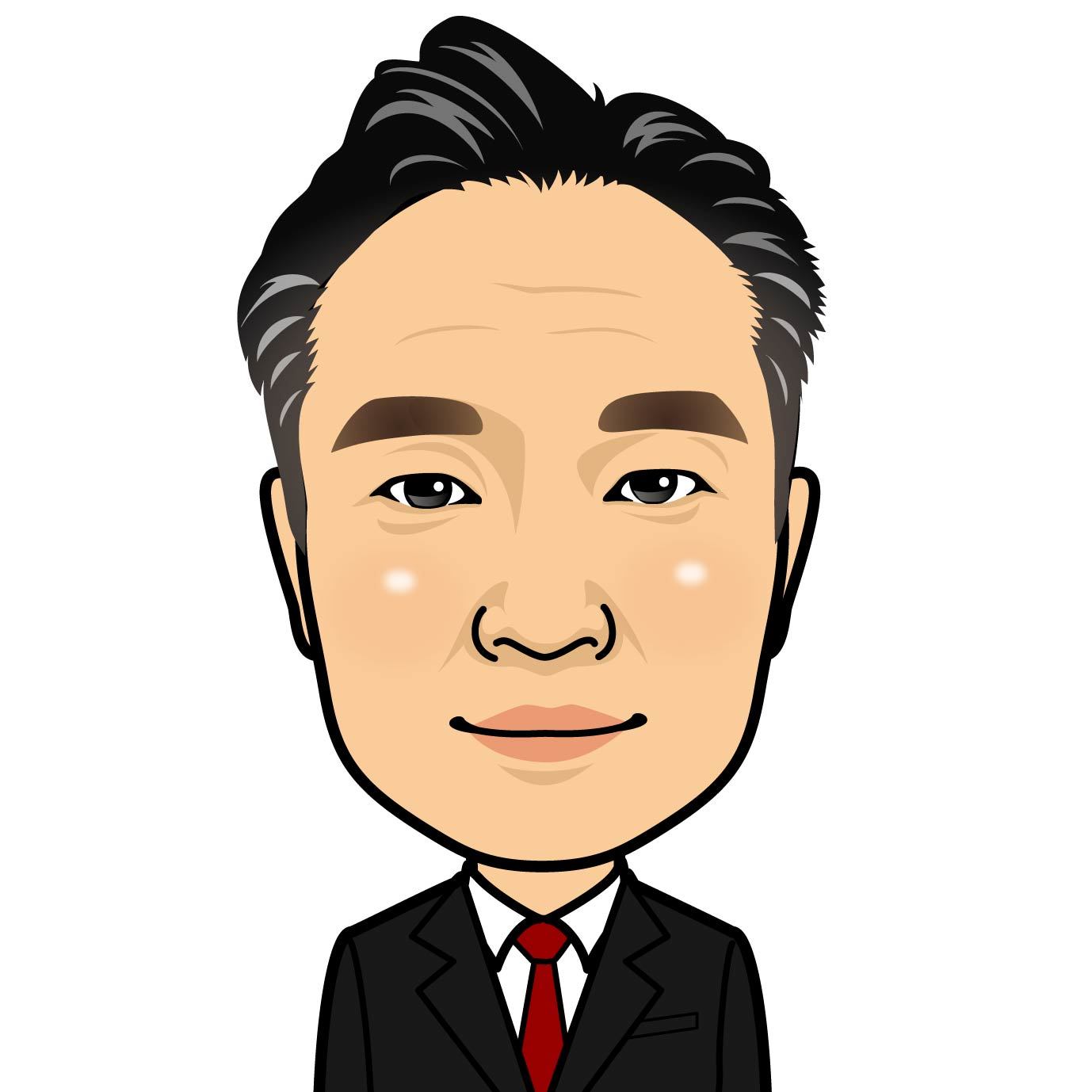
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計 給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ
給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ