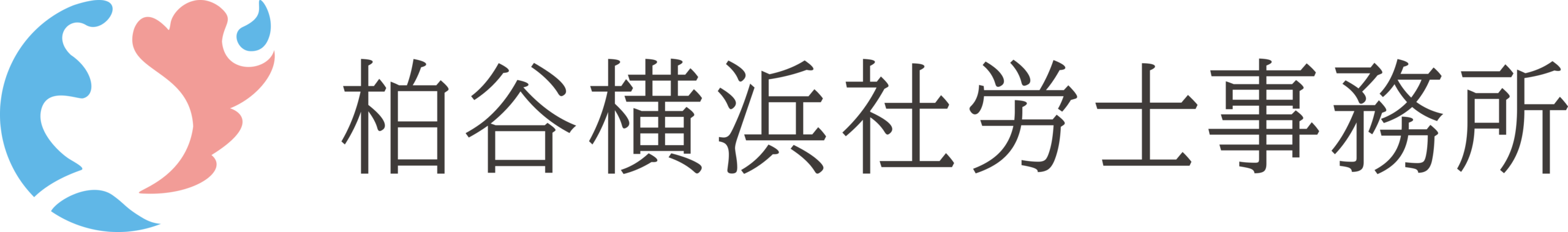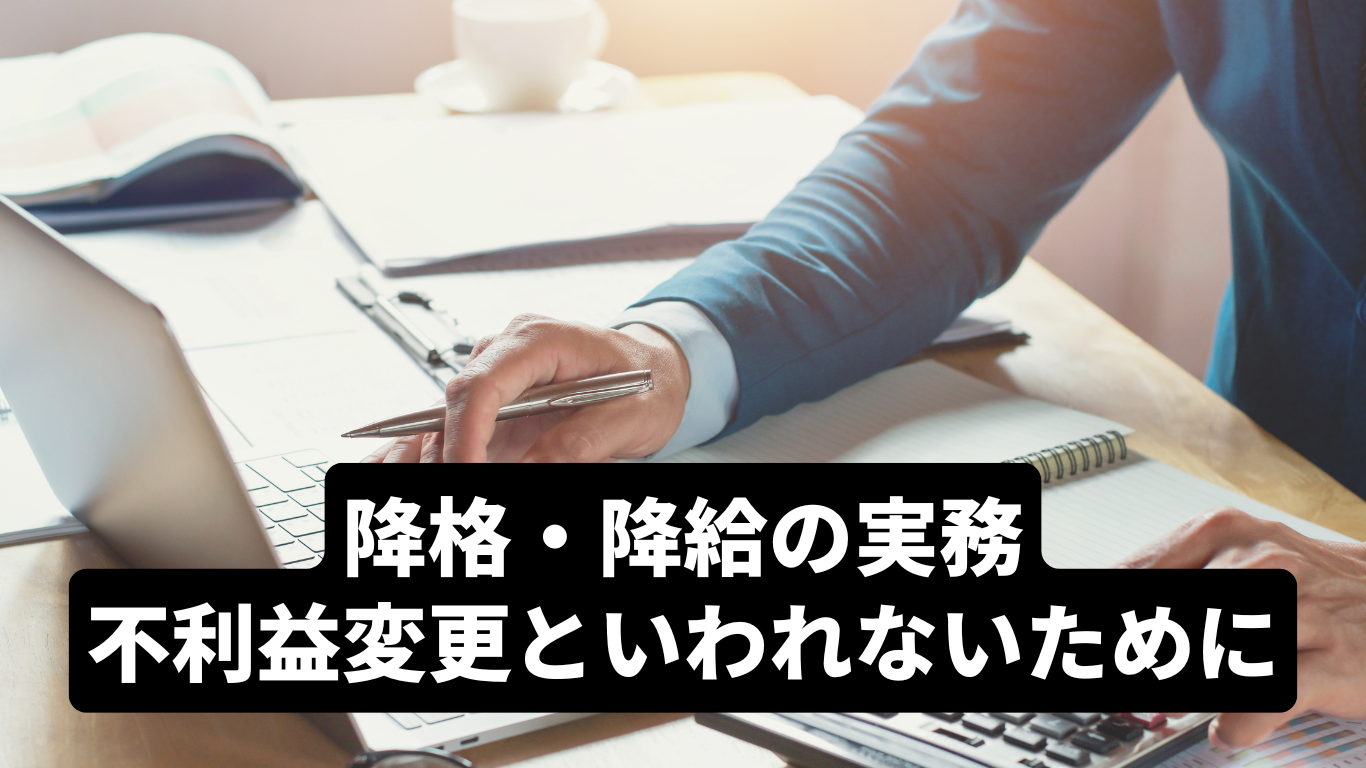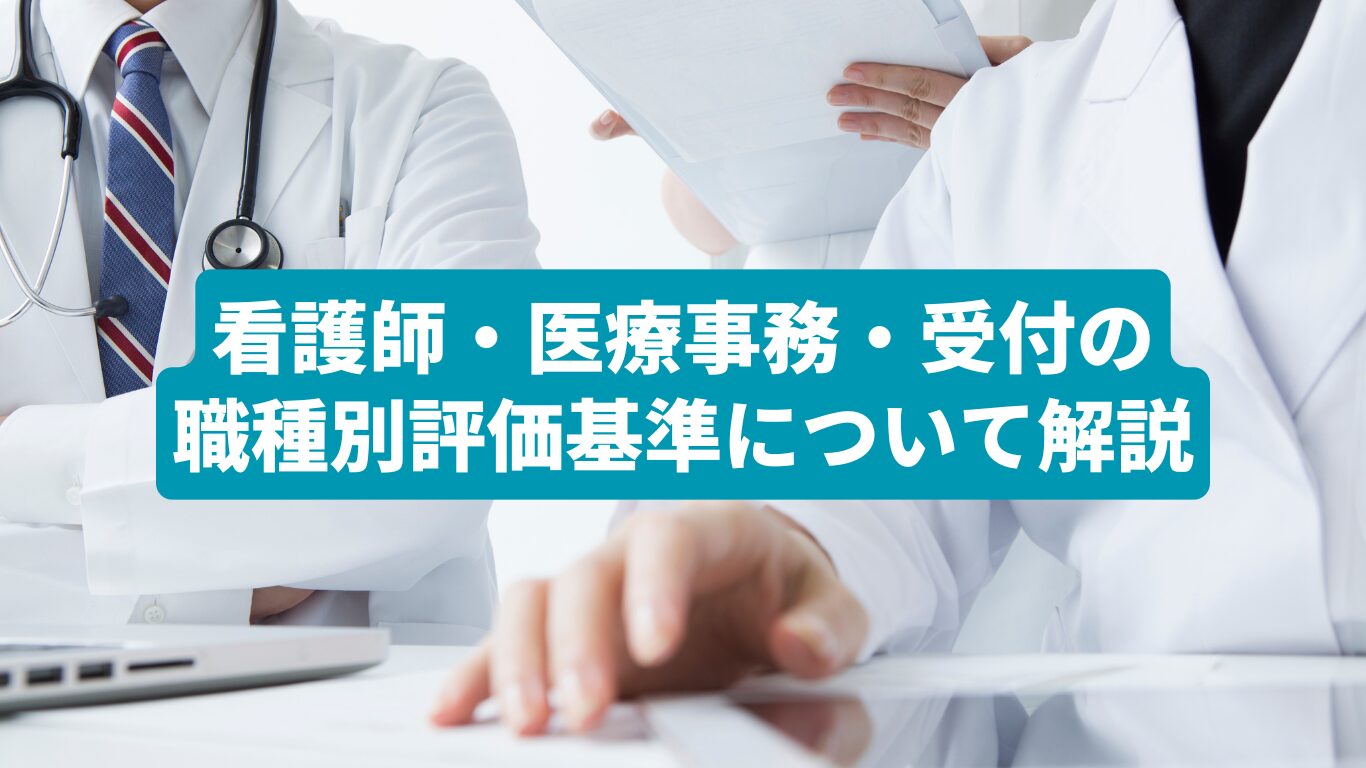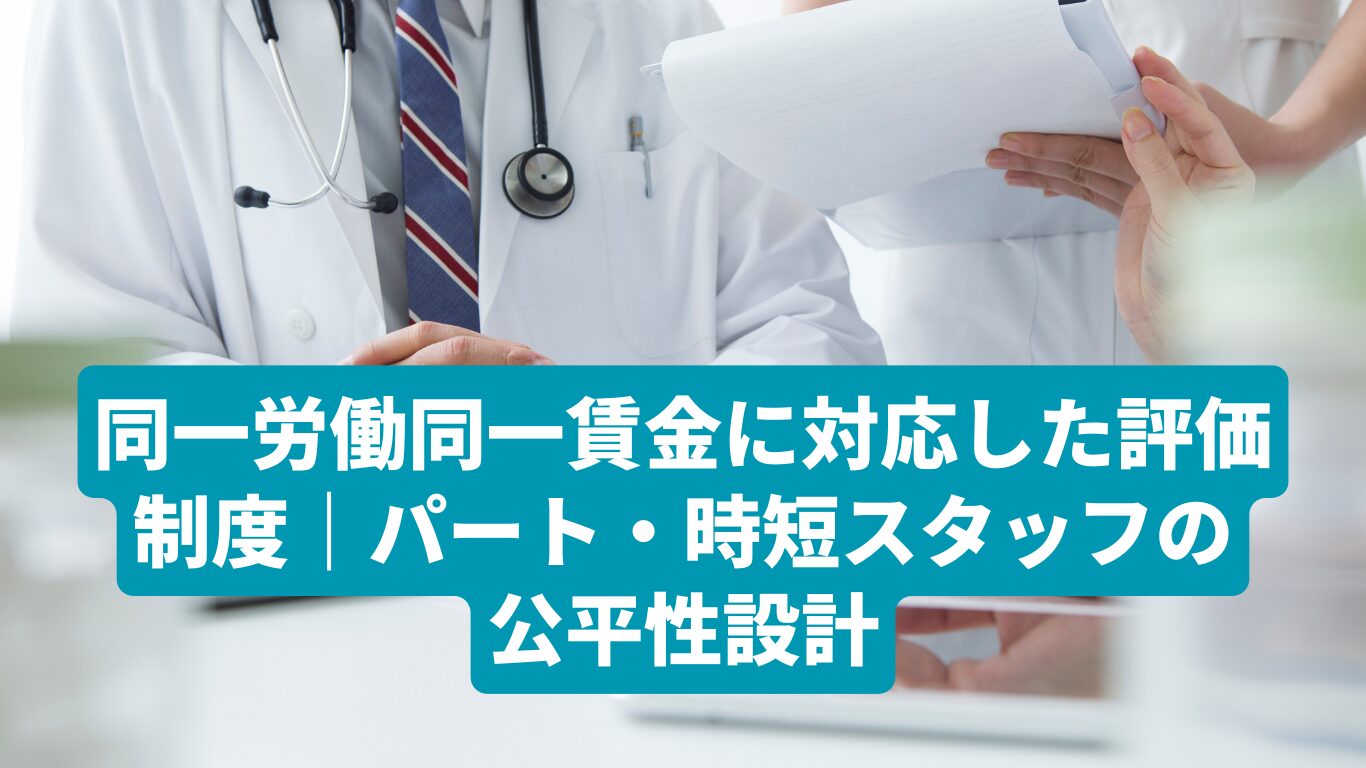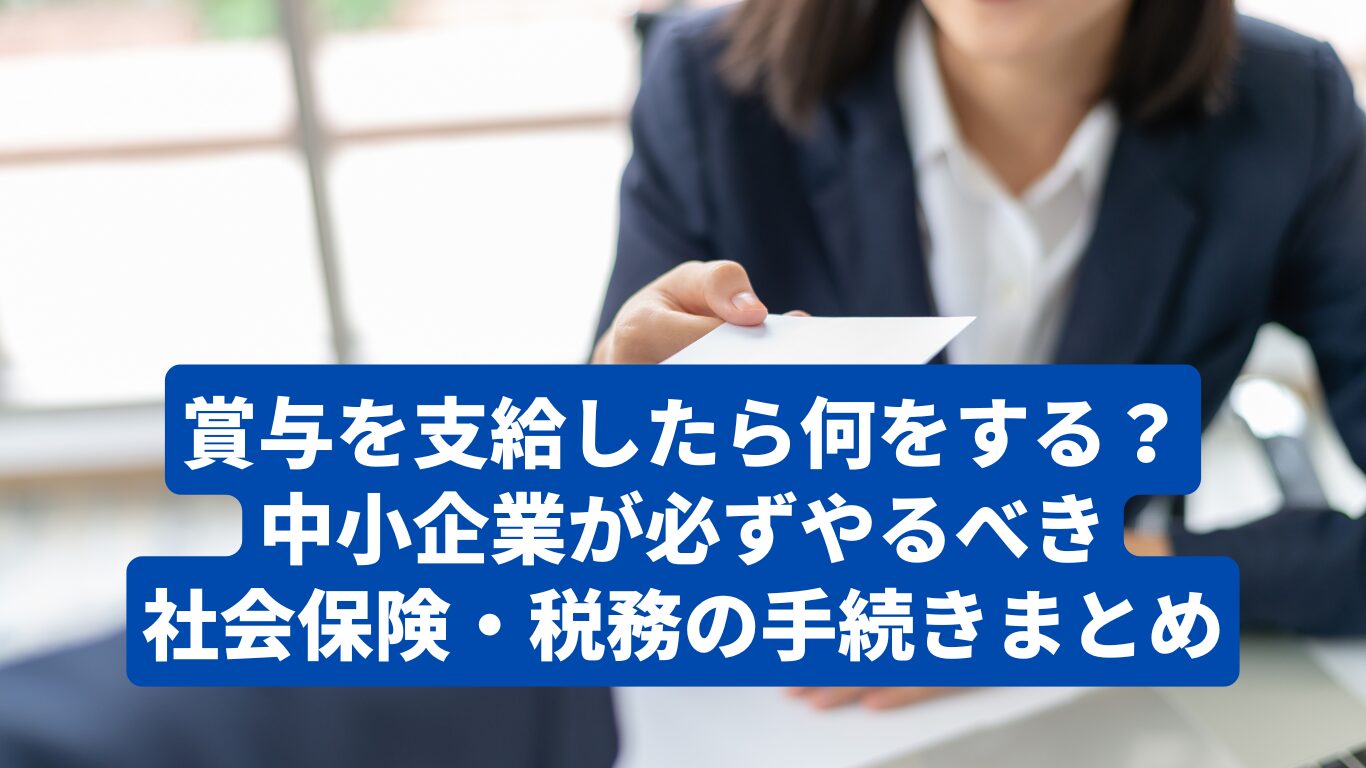はじめに
従業員の評価や会社の事情によって、どうしても降格や降給といった判断が必要になることがあります。ただ、その対応を間違えると、職場の雰囲気が悪くなったり、トラブルに発展してしまったりすることも。
この記事では、降格・降給についての基本的な考え方から、法的なポイント、トラブルを防ぐための工夫まで、企業の人事や管理職の方に役立つ内容をまとめてみました。
降格・降給とは何か?
降格と降給の定義と違い
「降格」は役職や職位が下がること、「降給」は給与の金額が下がることを指します。両方が同時に起きることもあれば、片方だけの場合もあります。
たとえば役職がなくなっても、給与はそのままというケースもありますし、評価が下がって給与だけが減るということもあります。従業員にとってはどちらもマイナスの変化になりますので、慎重に対応していく必要があります。
労働条件の不利益変更とは?
労働契約で決まっている条件を会社側の判断で変える場合、それが従業員にとって不利益な内容であれば「不利益変更」と言われます。降格や降給もその一つです。
このような変更をするには、就業規則にきちんと書かれていることや、本人の納得があることが重要になります。評価制度や説明資料などが整っていないと、「一方的に不当な扱いを受けた」と感じられてしまうかもしれません。
降格・降給の法的根拠と注意点
就業規則への明記の必要性
降格・降給を実施するには、まず就業規則や賃金規程にそのルールが定められていることが必要です。「こういう場合には降格や降給の可能性がある」といった内容が記載されていれば、企業としての対応にも一貫性が出ます。
例えば「業績評価に応じて等級や賃金が変わる」といった文言があれば、制度の一部として位置づけられ、トラブルになりにくくなります。もちろん、従業員への説明や周知も忘れずに行いましょう。
労働契約法における注意点
労働条件の変更は、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」(労働契約法第8条)とされています。
双方の合意があれば、変更が可能ですが、使用者が一方的に変更することはできません。
また、次の場合を除いて、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(労働契約法第9条)とされています。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情
に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする(労働契約法第10条)つまり、労働条件の変更は原則、労使双方の合意。就業規則の変更の場合は、その内容が合理的であること、しっかりと周知がされていることが必要になります。
判例から見る降格・降給の合法性基準
過去の裁判例を見てみると、降格・降給が認められたケースでは、「就業規則に明記されていた」「評価制度が明確だった」「本人に説明が行われていた」といった点がそろっていることがやはり多く、逆に、制度が曖昧だったり、説明がなかったりすると、処遇変更が無効と判断されるケースもあります。対応する際は、制度の整備と運用の透明性をセットで考える必要があります。
降格・降給を検討する際の実務ポイント
降格・降給が認められる正当な理由
従業員の評価や業務の見直しをしていると、「このポジションでは難しいかも…」と感じることもあると思います。
そんなときに出てくるのが「降格」や「降給」といった判断です。
ただし、当然ながら、会社側が一方的に対応するわけにはいきません。能力不足や業務成績の低下、組織改編など“正当な理由”があることが前提になります。感情的な判断や個人的な相性での処遇変更は、後々のトラブルのもとになりますので注意が必要です。
評価記録や指導履歴などをしっかり残しておきましょう。
人事評価との整合性確保の重要性
「評価制度」と「実際の処遇変更」がかみ合っていないと、「なぜ自分が降格?」という不満につながってしまいます。
処遇変更をする際は、評価結果が具体的であることがとても大切です。「何をどのように評価して、その結果どうなるのか」が明確であれば、納得してもらいやすくなります。
面談の場などで、評価のフィードバックと合わせて、求められる役割などをすり合わせておくと、後の処遇変更もスムーズです。
手続きにおける透明性と公平性の確保
「公平性」と「透明性」、これは人事制度の信頼性を保つために欠かせません。
誰がどんな基準で判断したのか、どんな手順を踏んだのかが見える形になっているかどうか。
とくに降格や降給といったネガティブな変更の場合、説明や記録があいまいだと従業員の不信感を招きやすくなります。
説明の場を設ける、本人の意見を聞く、記録をきちんと残す――そんな小さな積み重ねが、後のトラブルを防ぐカギになります。
降格・降給をめぐるトラブル防止策
事前の十分な説明と同意取得
降格・降給のような重要な変更は、いきなり通告するのではなく、きちんと話し合いの場を持つことが大切です。
「なぜそうなるのか」「これまでどうだったのか」「今後どうしていくのか」、こうしたことを丁寧に説明することで、従業員も納得しやすくなります。
個別合意書や同意書作成時のポイント
「言った・言わない」のトラブルを避けるためにも、処遇変更の際には同意書や合意書の作成が欠かせません。
合意書には、処遇変更の理由・内容・開始日などをきちんと記載します。給与に関係する場合は、変更後の金額や手当の扱いも明確にしておきましょう。
場合によっては、社会保険料の変更や雇用契約内容の見直しが必要になることもあるので、必要に応じて社労士や専門家に確認するのがおすすめです。
労働者への心理的配慮の方法
降格・降給は、従業員にとって精神的な負担が大きいものです。
だからこそ、「どう伝えるか」「どう支えるか」がとても重要になります。
話すタイミングや場所、言葉の選び方はもちろん、今後のサポート体制についても具体的に伝えておくと安心感につながります。
処遇変更後も、定期的にフォロー面談をしたり、相談できる窓口を用意したりして、孤立しないように工夫していきましょう。
降格・降給が認められないケース
懲罰的降格・降給の問題点
業務上の理由ではなく、「処分として降格」「罰としての降給」といった対応をしてしまうと、法的に問題になる可能性があります。
懲戒処分としての対応をする場合は、就業規則にしっかりと規定があることや、懲戒の手続き(弁明の機会など)をきちんと踏んでいることが前提になります。
「とりあえずポジションを下げておこう」「給与を減らしておけばいい」といった曖昧な対応は、あとからトラブルにつながるので要注意です。
不当な理由とされやすい具体例
以下のようなケースは、「不当な降格・降給」として争いになる可能性が高いです。
- 上司に反論した、意見を言ったことへの仕返しのような対応
- 労働組合活動や社内の問題提起をした人への報復的な処遇変更
- 評価の基準が不明確なまま、突然の降格・降給
- 業績や行動に関係のない人間関係を理由にした判断
処遇の変更には「理由」と「証拠」がセットであることが前提です。対応を検討する際には、感情的にならず冷静に判断しましょう。
判例から学ぶNGケースの特徴
過去の裁判例では、次のようなポイントで処遇変更が無効と判断されることが多く見られます。
- 評価制度や処遇ルールがそもそも社内に整備されていなかった
- 本人に理由説明がなく、突然の通告になっていた
- 降格・降給の後、フォローアップの機会が全く設けられていなかった
「制度がない」「記録がない」「説明していない」この3つがそろうと、かなりリスクが高くなります。制度設計や手続き面も含めて、今一度見直しておきましょう。
降格・降給に関する就業規則の整備
降格・降給条項の必要性
就業規則の中に、降格や降給に関する内容がしっかりと明文化されていますか?
たとえ運用している評価制度があっても、就業規則や賃金規程に反映されていないと「そんな制度は知らなかった」と言われてしまいます。
社内での運用を支える“公式なルール”として、降格や降給についても記載しておきましょう。
具体的な記載事項
たとえば次のような内容を就業規則・賃金規程に明記しておくと、実務で使いやすくなります。
- 降格・降給が行われる可能性とその理由(評価・業務再編など)
- 手続きの流れ(評価、面談、決定、通知)
- 降給の場合の新しい給与体系の説明
- 昇格・昇給の再チャレンジ制度があること
規則に書くときは「できるだけ具体的に」がポイントです。
従業員への周知方法
せっかくルールを整備しても、「知らなかった」「聞いてない」となってしまっては意味がありません。
- 社内イントラネットでいつでも見られるようにする
- 制度導入時に説明会を開く
- 評価制度とセットで説明する
といった形で、従業員の目に届く・理解につながるような周知の工夫が必要です。
「納得できる制度」は、「伝わる制度」でもあります。
降格・降給後のフォローアップ
モチベーション維持のための施策
降格や降給を受けた従業員のモチベーション、気になりますよね。
本人からすると「評価されていない」と感じるわけですから、そのままにしておくとパフォーマンスや職場全体の空気に影響が出てしまうことも。
だからこそ、処遇変更後のフォローが大切です。
たとえば、次のような取り組みが効果的です。
- 期待している役割を明確に伝える
- 小さな目標を設定して成功体験を積ませる
- 面談などでこまめにコミュニケーションを取る
前向きな行動をサポートする姿勢を見せることで、信頼関係の再構築にもつながります。
キャリアパスの再設計
「降格=後戻り」ではなく、「リスタートの機会」として捉えてもらえるようにしたいですよね。
そのためには、キャリアの再設計が必要です。
たとえば、
- 新しいスキルの習得支援
- OJTや研修の再チャレンジ
- 中長期的な目標の見直し
など、今後の成長に向けた具体的なサポートを用意しておくと、本人も前向きになりやすくなります。
制度として「再チャレンジの道筋」があると、他の従業員にとっても安心材料になります。
再評価の機会の提供
一度処遇が下がると、「このまま評価されないのでは?」という不安を感じる人も多いです。
そんな不安を解消するために大切なのが、定期的な再評価の仕組み。
- 評価期間をあらかじめ決めておく
- 希望者には面談の機会を設ける
- 明確な基準に基づいたフィードバックを行う
こうした仕組みがあることで、「がんばれば戻れる」「評価してもらえる」という信頼感を持ってもらいやすくなります。
労使トラブルを防ぐための注意点
公平性・透明性の確保
「なんであの人だけ?」「自分だけが不公平では?」
処遇変更に関して、こんな声が出ないようにするには、制度の“見える化”がカギです。
- 評価の基準や手順が整っているか
- 誰にでも同じ基準が適用されているか
- 説明責任をきちんと果たしているか
こういった点を見直しておくことで、周囲の納得感も高まりやすくなります。
記録の重要性
「記録があるかないか」で、トラブルになったときの対応は大きく変わります。
- 評価結果や面談記録
- 処遇変更の説明内容
- 合意書や同意書の控え
これらをしっかり残しておくことで、あとから「言った・言わない」にならずに済みます。
とくに社内で複数人が関わる場合は、記録の共有も忘れずに。
労働組合や従業員代表との協議
労働組合がある会社では、制度の導入や処遇変更を行う際、事前に協議しておくのが基本です。
組合との対話は面倒に感じられることもあるかもしれませんが、実は後のトラブル防止につながる大事なステップです。
組合がない場合でも、従業員代表との意見交換をすることで、制度への理解や納得度が高まります。
まとめ
降格・降給は、会社にとって避けられない場面もありますが、実施の仕方次第で大きな違いが出ます。
「理由がきちんとあるか」「制度として整っているか」「説明がされているか」「フォローができているか」
こうしたポイントを押さえておけば、トラブルを防ぎつつ、従業員との信頼関係も保ちやすくなります。
従業員にとって納得できる対応ができるかどうか、改めて見直してみてください。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
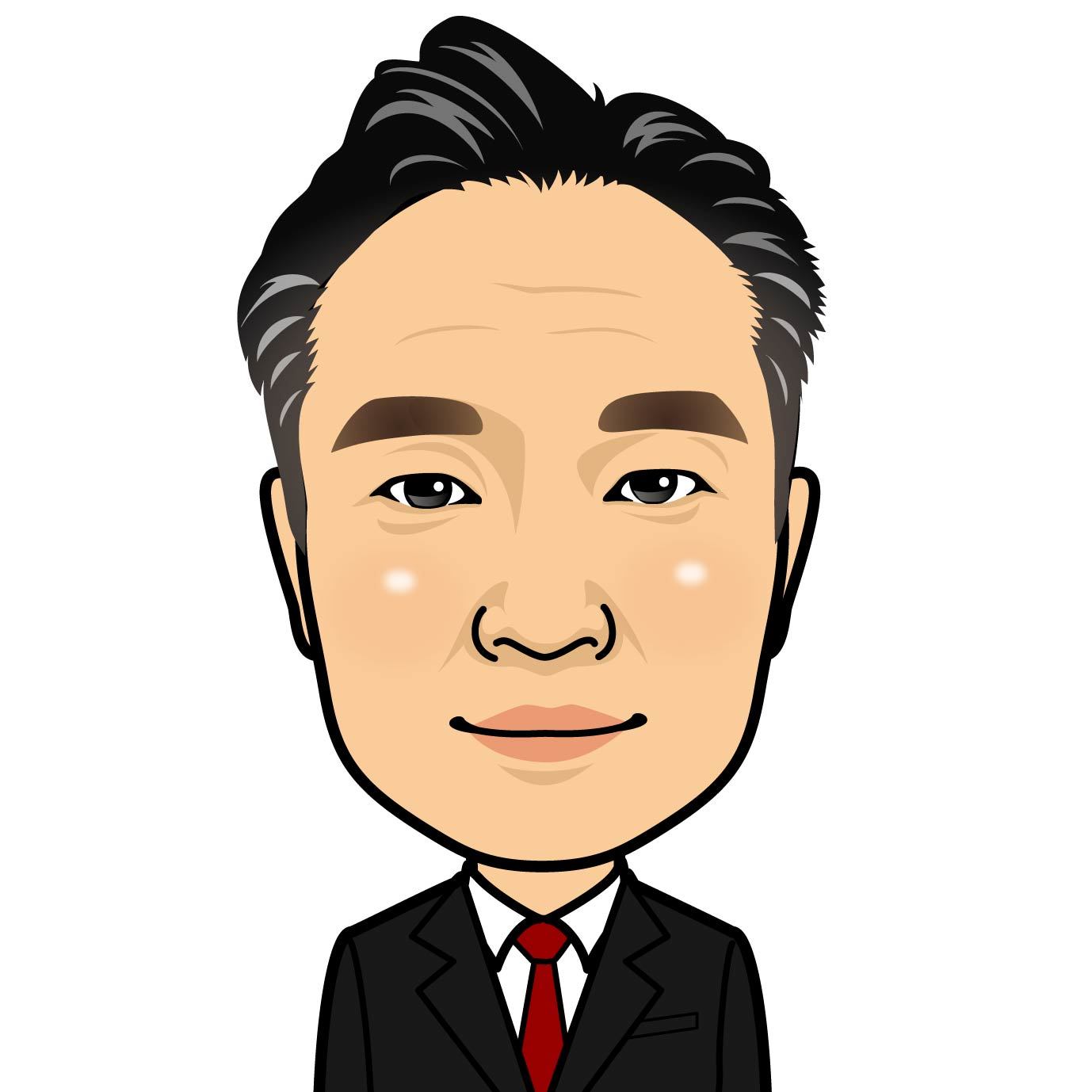
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計 給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ
給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ