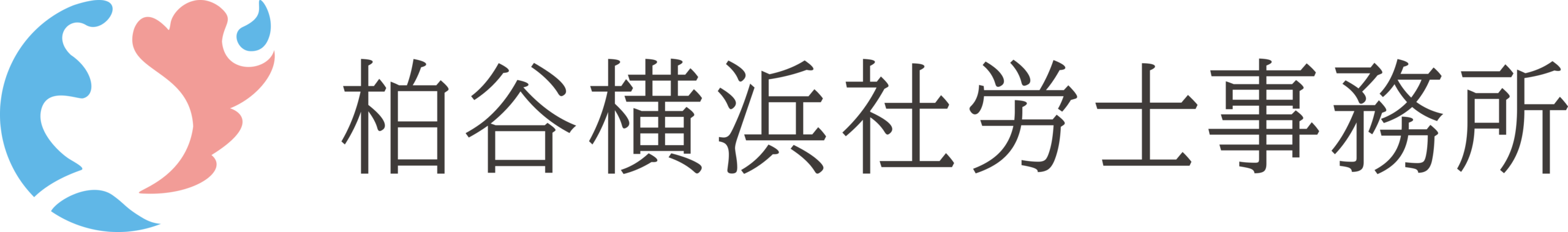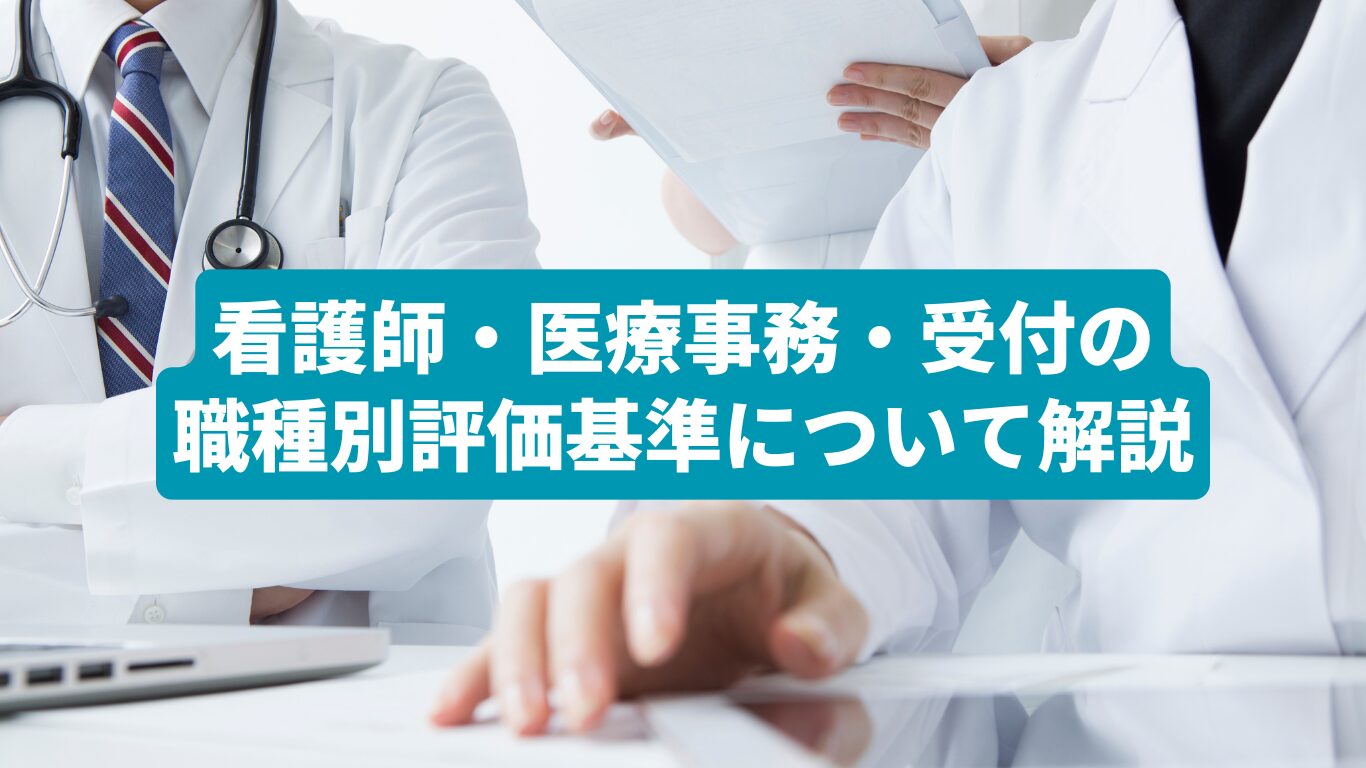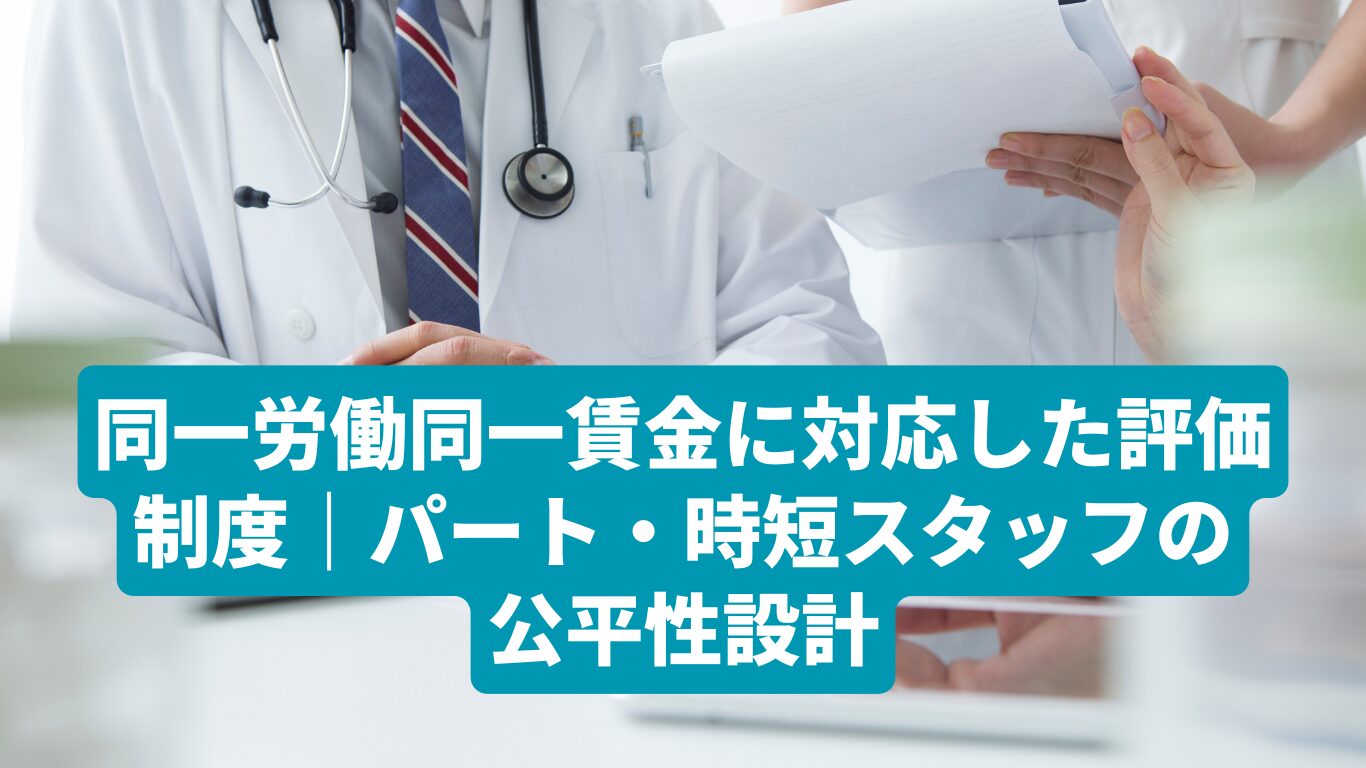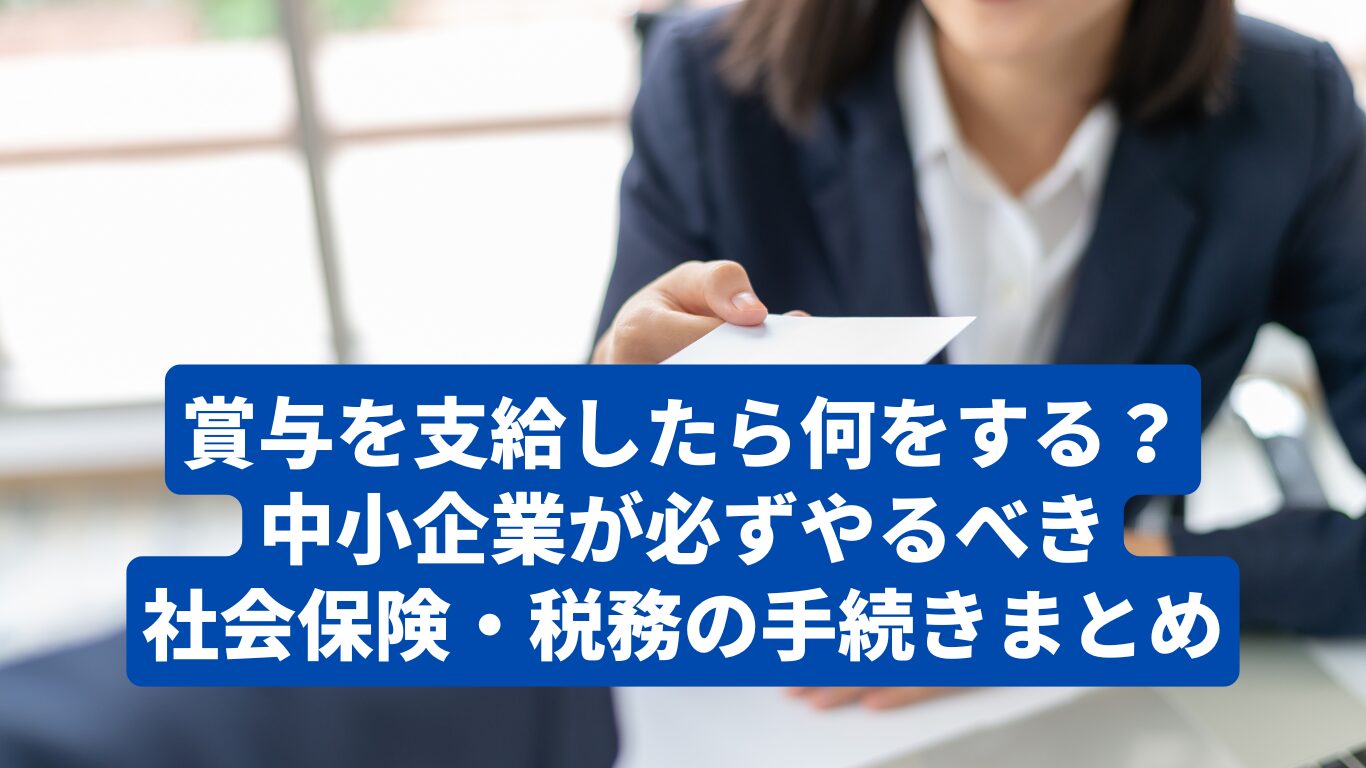1年単位の変形労働時間制とは?
1カ月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
夏休みや年末年始休みなどの長期休暇の時期が繁忙期である旅館や行楽地での業種、お中元やお歳暮・セールの時期などが繁忙期であるデパート・スーパーなど、月によって業務に繁閑のある会社で、繁忙期は労働時間を長く設定し、閑散期には短い労働時間を設定することにより、年間の総労働時間の短縮を図ることができます。
1日・1週間の労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制での労働時間の限度は1日10時間・1週52時間までです。
また、対象期間が3カ月を超える場合、以下の制限があります。
- 対象期間中に、週48時間を超える所定労働時間を設定するのは、連続3週間以内とすること
- 対象期間を初日から3カ月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数が3以内とすること
労働日数の限度
対象期間における労働日数の限度は1年間に280日です。対象期間が3カ月以内の場合、制限はありません。
ただし、1年間の総労働時間の上限は「2085.71時間」ですので、年間280日出勤とする場合、1日の労働時間は7.4時間程度におさえる必要があります。
対象期間における連続労働日数
連続労働日数は、原則として最長6日です。
ただし「特定期間」を設ければ、1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)まで可能です。
第1週 (日曜休み) 出勤:月 火 水 木 金 土
第2週 出勤:日 月 火 水 木 金 (土曜休み)
残業時間の計算方法
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の残業の計算方法は以下の通りです。
- 1日については、8時間を超える定めをした日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間については、40時間を超える定めをした日はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
- 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
決められた特定の日・週については、1日8時間・週40時間を超えた労働に対して残業代が発生しません。ただし、設定した労働時間を超える勤務があった場合は別途残業代が必要です。
また、途中採用者・途中退職者は実労働時間に応じて、以下のように再計算する必要があります。
繁忙期に多く働いた従業員が閑散期の前に退職したような場合、平均週40時間を超えて労働をしたことになることがあるため。
「実労働期間における実労働時間-実労働期間における法定労働時間の総枠(※)-実労働期間にすでに割増賃金を支払った時間外労働」
※実労働期間における法定労働時間の総枠=(実労働期間の暦日数÷7日)×40時間
1年単位の変形労働時間制の採用方法
1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定を締結し、下記の事項を定め所轄労働基準監督署に届け出ます。10人以上の労働者がいる会社ではあわせて就業規則に記載した上で、所轄労働基準監督署に届け出ます。
- 対象労働者の範囲
※年少者(満18歳未満)は1週48時間、1日8時間以内のみ可能。残業しない旨の請求をした妊産婦は不可。 - 対象期間(1カ月を超え1年以内の期間に限る)および起算日
- 特定期間(対象期間のうち特に業務が繁忙な時期として定める期間)
- 労働日及び労働時ごとの労働時間
※1年間の所定労働時間の総枠は「40時間÷7×365日=2085.71時間」 - 1日8時間勤務の会社は1年間の出勤日数を260日以内にすれば1週40時間以内となります。
- 労使協定の有効期間
変形労働時間制のメリット
- 業務の繁閑にあわせて事前に労働時間を設定することにより、柔軟な働き方ができ、残業代の抑制ができる。
- 1年を通して調整するので、閑散期や祝祭日が多い月の出勤日数や労働時間が減れば、その分だけ他の月の出勤日数や労働時間にあてられる。
変形労働時間制のデメリット
- 年間カレンダー、月ごとの所定労働日数、労働時間数を事前に決めて周知が必要なため準備が大変。
- 毎年労使協定を提出する必要がある。
- 残業計算は、設定した日ごと、週ごと、そして総労働時間を集計する必要があり、煩雑になる。
- 繁忙期には、長く働くので身体がきつい。
- 従業員が制度を理解しておらず、残業代をもらえていないと不満を持つ。
1年単位の変形労働時間制を採用する場合の注意点
1カ月単位の変形労働時間制同様、事前に労働時日数・労働時間数を決めて周知する必要があります。
残業計算もその設定した時間数に応じて計算が必要です。「うちは変形労働時間制だから残業代は全くない」と勘違いしているケースもあります。
導入に当たっては、しっかりと手順を踏んで、従業員にも理解してもらうことが必要です。
中小企業の経営者様・クリニックの院長様必見!!
中小企業やクリニックの人事労務・組織づくり・人事評価・採用に役立つ資料を無料でダウンロードできます!日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら
投稿者プロフィール
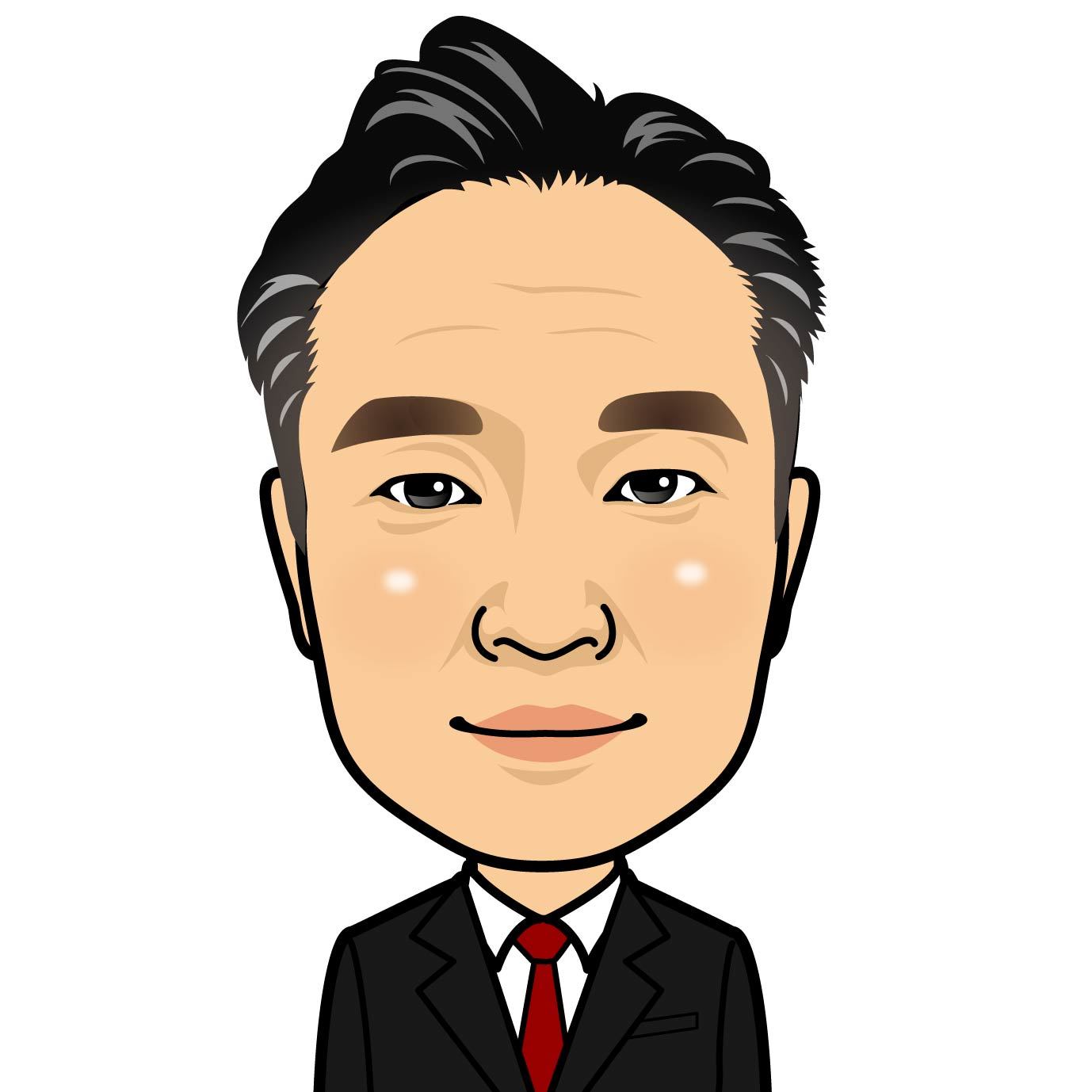
-
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
最新の投稿
 クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説
クリニック2026年1月6日看護師・医療事務・受付の職種別評価基準について解説 クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ
クリニック2025年12月15日残業を減らすクリニックの評価観点:片付け・引き継ぎ・声かけ クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計
クリニック2025年12月8日同一労働同一賃金に対応した評価制度|パート・時短スタッフの公平性設計 給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ
給与計算2025年11月19日賞与を支給したら何をする?中小企業が必ずやるべき社会保険・税務の手続きまとめ