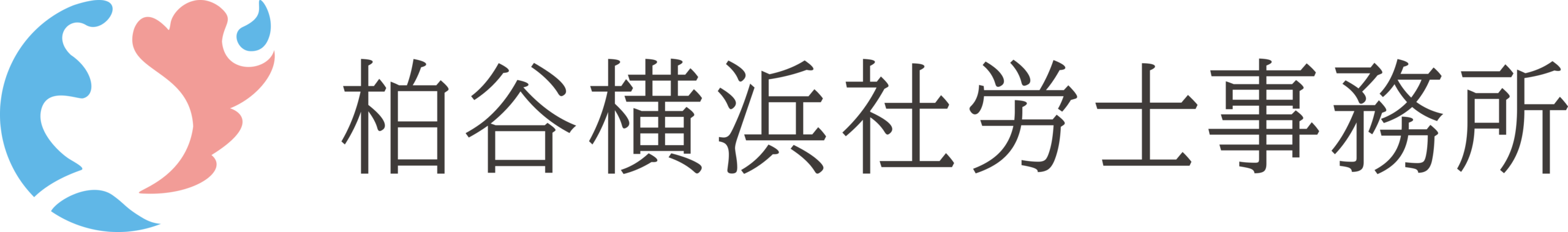労務管理
-

令和5年度の健康保険料率が変更されました
令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険料率が変更されました。 令和5年度 保険料率について(神奈川) 神奈川県健康保険料率は、9.85%から10.02%、介護保険料率は1.64%から1.82%に上がっています。給与計算の際には、注意しましょう。
-

令和5年度の雇用保険料率が変更されました
令和5年4月1日からの雇用保険料率が変更されました。 令和5年度雇用保険料率のご案内 • 失業等給付等の保険料率は、6/1,000に変更になります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000) 事業主は、失業等給付等の分と雇用保険二事業の分を負担します。従業員負担分の保険料は月々の給料から天引きし、会社が…
-

社会保険適用拡大。任意特定適用事業所の申し出とは?
令和4年(2022年)10月から、従業員数が101人以上の企業で働く短時間労働者も、新たに社会保険の適用対象となりました。これにより社会保険の適用となった事業所は「特定適用事業所」と呼ばれます。 短時間労働者とは 短時間労働者とは、以下の方です。 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上(2) 2カ月を超えて使用され…
-

養育期間標準報酬月額特例とは?育児短時間勤務で給料が下がったら出しておく!
令和4年10月から産後パパ育休といわれる男性の育児休業制度も始まりました。育児休業が柔軟に取得できるようにと様々な改正が行われていますが、以前からある「養育期間標準報酬月額特例」という制度があることはあまり知られていません。 養育期間標準報酬月額特例とは? 養育期間標準報酬月額特例とは、厚生年金保険の特例措置です。子ど…
-

振休と代休の違いとは?割増賃金も再確認。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間と定めれています。また会社は労働者に対して、週に1日又は4週間に4日以上の「法定休日」を与えなければいけません。このため多くの会社が1日8時間で土日休みの週40時間という設定になっています。この休日に休日出勤を命じた代わりに与える休日に「振替休日」と「代休」があります。それぞれの違…
-

休憩を交代で取らせるときは、「 一斉休憩の適用除外に関する労使協定」が必要です。
新型コロナウィルス対策として密を避けるためテレワークも促進されましたが、その後通常出社に戻った会社も多いようです。東京に向かう朝の通勤電車も結構込み合っています。 厚生労働省から出されている「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の中に、<昼休みの時差取得>があります。 昼休みの時間を分散させること…
-

法人化した場合の労働保険、社会保険の手続き
起業、独立した場合、最初から株式会社等の法人を設立して始める場合と、副業や個人事業主として始めた事業を法人化する場合とがあります。 今回は、個人事業から法人化した場合の必要な手続きについて、見ていきましょう。 労災保険 個人事業の場合でも、従業員を雇用していれば、労災保険の加入は必須です。労災保険は、従業員の業務中や通…
-

役員や社長の家族は雇用保険に加入できる?
起業し、従業員を雇った時は、労災保険、雇用保険の手続きが必要です。雇用保険料は、従業員が退職した時の失業保険等に充てられます。 従業員を雇用した際の手続きは、「保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」とは?人を雇ったら必ず加入!をご参照ください。 では、役員や社長の家族は雇用保険に加入できるのでしょうか? 役員や社…
-

令和4年10月から雇用期間が2ヵ月以内でも社会保険へ加入。
「うちの会社は、試用期間が終わったら社会保険に入れている。」「週30時間働いているパートがいるけど、本人が社会保険加入はしたくないと言っている。」 中小企業では、まだまだよく聞くフレーズですが、正しくありません。加入要件を満たせば、入社日から当然に加入しなければいけません。 社会保険加入要件 強制適用事業所株式会社など…
-

建設業の時間外労働の上限規制は2024年から!
2024年(令和6年)4月1日から建設業でも、時間外労働の上限規制が始まります。 原則の法定労働時間 法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。これを超える労働がある場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を従業員代表と締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。この時間外労働の上限は、月45時間…